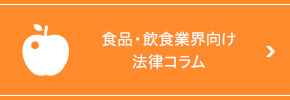特別受益に関するQ&A
Contents
- 1 1. はじめに
- 2 2. 特別受益の概要
- 2.1 Q. 特別受益とは何ですか?
- 2.2 Q. 特別受益は、相続において、どのように扱われるのですか?
- 2.3 Q. 被相続人より先に、推定相続人1が死亡してしまいました。このような場合、特別受益についてはどのようになりますか?
- 2.4 Q.婚約者に5000万円を贈与し、その後に結婚しました。婚約者への贈与は特別受益にあたりますか?
- 2.5 Q. 被相続人の子が結婚し、被相続人は子の配偶者Xに贈与しました。その後、被相続人とXが養子縁組しました。Xへの贈与は特別受益にあたりますか?
- 2.6 Q. 被相続人が、相続人Cの配偶者Eや子Fへ財産を贈与しました。この贈与はCに対する特別受益に当たりますか?
- 2.7 Q.持戻しの対象となる「婚姻」のため受けた贈与とは、具体的にどのようなものですか?
- 2.8 Q. 養子縁組のため」受けた贈与とは、具体的にどのようなものですか?
- 2.9 Q. 持戻しの対象となる「生計の資本として」受けた贈与とは、具体的にどのようなものですか?
- 2.10 Q. 毎月、親から決まった額の送金を受けていますが、これは特別受益に当たりますか?
- 2.11 Q. 相続分の譲渡は「贈与」として特別受益に当たりますか?
- 2.12 Q. 被相続人は生命保険に入っていました。共同相続人の一部が取得した死亡保険金は、特別受益に当たり、持戻しの対象となりますか?
- 2.13 Q. 死亡保険金は、原則として持戻しの対象とはならないものの、例外的に、特段の事情がある場合には持戻しの対象になることが分かりました。では、特段の事情が認められた場合、何が持戻しの対象となるのでしょうか?
- 2.14 Q. 死亡退職金請求権は、持戻しの対象となりますか?
- 2.15 Q.遺族年金は、持戻しの対象となりますか?
- 2.16 Q. 特別受益に当たる財産から生じた果実も、特別受益に含まれますか?
- 2.17 Q. 相続人の1人が生前に被相続人から贈与を受けていましたが、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」受けた贈与ではないから、特別受益に当たらない、と主張して、他の相続人と争いになっています。このような場合はどうしたら良いでしょうか?
- 2.18 Q. 相続人である私は、被相続人から賃借した土地上に建物を建てて居住しています。月々の賃料は支払っていますが、権利金は支払っていません。権利金を支払わなかったことは、特別受益に当たりますか?
- 2.19 Q. 相続人である私は、被相続人が所有する(民法206条)土地を無償で借り(使用貸借:民法593条)、その上に建物を建てて居住しています。このような土地の無償利用は特別受益に当たりますか?
- 2.20 Q. 相続人である私は、被相続人の所有する建物を無償で使用してきました。特別受益に当たりますか?
- 2.21 Q. 「相続させる」旨の遺言による受益も、特別受益として持戻しの対象となりますか?
- 2.22 Q. 特別受益に該当するためには、贈与の期間制限等はありますか?
- 2.23 Q. 特別受益は、必ず相続財産に加えて計算しなくてはいけないのですか?
- 2.24 Q. 「推定する」(民法903条4項)とは、どういうことでしょうか?
- 2.25 Q. いつの時点で婚姻期間が20年以上であれば良いのでしょうか?
- 2.26 Q. 特別受益の評価基準時はいつですか?
- 3 3. 持戻し免除の意思表示
- 4 4. 特別受益と遺留分
- 5 5. おわりに
1. はじめに
共同相続人間の公平を図る制度として、特別受益の持戻し(民法903条1項)というものがあります。こちらは遺留分侵害額請求制度(民法1046条1項)ほど直接的には問題とならないものの、事業承継において付随的に問題となることがあり、事業承継の際にはこれにも配慮する必要があります。そこで、本ページでは、特別受益についてQ&A形式でご説明します。
2. 特別受益の概要
Q. 特別受益とは何ですか?
A. 共同相続人のうち、被相続人(亡くなった方)から、遺贈(民法964条(※1))や「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」贈与(民法549条、554条)を受けた者がいる場合、当該遺贈や贈与によって得た利益のことを「特別受益」といいます(民法903条1項)。
贈与に伴う特別受益に関しては、上述の通り、その目的が婚姻(民法739条1項)・養子縁組(後述の通り、普通養子縁組に限る:民法799条、739条1項)・生計の資本のためであるものに限定されますが、遺贈に伴う特別受益に関しては、目的は不問です。
(※1)遺贈:遺言によって自己の財産の全部又は一部を他人に譲り渡すこと。「贈与」が贈与者及び受贈者(贈与を受ける者)双方の意思表示の合致に基づく契約行為(民法522条1項)であるのに対し、遺贈は遺言者が単独できる点で異なります。
Q. 特別受益は、相続において、どのように扱われるのですか?
A. 各相続人の具体的相続分を計算するにあたり、計算の基礎となる被相続人の相続財産(いわゆる遺産)に、特別受益とされた遺贈や贈与の価格を加算して計算します(民法903条1項)。
これを「持戻し」といいます。共同相続人間の公平を図るために、規定されているものです。
事例1
夫Aが亡くなり(民法882条)、妻B、長男C、長女Dが共同相続人となりました(民法890条前段、887条1項)。
Aの遺した相続財産は預貯金1億円であり、Aは遺産の分配方法について、遺言で何も指定していませんでした。
事例1の場合、遺産の分配については、法定相続分に従う(民法900条、901条)ことになります。法定相続分は、妻Bが2分の1(民法900条1号)、長男CとDがそれぞれ4分の1(民法900条4号本文)です。その為、B・C・Dの法定相続分に基づく相続財産の価格は、それぞれ5000万円、2500万円、2500万円になります。
しかし、仮に、共同相続人の内Dだけが、Aが亡くなる直前に婚姻や生活の費用として2000万円の贈与を受けていたとしたらどうでしょうか。Dは、実質的には、2500万円+2000万円=4500万円を受け取っており、B・Cとの関係で公平を欠くと言えます。
このように、共同相続人のうち被相続人から遺贈や贈与によって特別の利益を得た者がいる場合における、不公平の是正のための制度が、特別受益の持戻しです。被相続人から相続人への遺贈や贈与を「遺産の前渡し」、すなわち「特別受益」と考え、相続分の計算にあたり相続財産に加算して計算することで、共同相続人間の公平を図っているのです。
事例1の場合、各相続人の具体的な相続分の計算のもととなる財産(これを「みなし相続財産」といいます。)は、1億円+2000万円(特別受益の持戻し)=1億2000万円です。そして、このようにして計算されたみなし相続財産をもとに、法定相続分に従ってB・C・Dの本来の相続分(特別受益に当たる遺贈や贈与が無かった場合のB・C・Dの相続分)を計算すると、それぞれ、6000万円、3000万円、3000万円となります。そして、Dは既に2000万円の贈与を受けているので、その分を差し引き、3000万円-2000万円=1000万円のみを相続することになります(これを「具体的相続分」といいます)。その結果、Bは6000万円、Cは3000万円、Dは1000万円をそれぞれ相続することとなります。
Q. 被相続人より先に、推定相続人1が死亡してしまいました。このような場合、特別受益についてはどのようになりますか?
A. 被相続人より先に推定相続人が死亡した場合、死亡した推定相続人(※1)に子がいれば、その子が推定相続人に代わって相続人となります。これを代襲相続といいます(民法887条2項本文)。そして、死亡した推定相続人を被代襲者、その子のことを代襲者といいます。
(※1)推定相続人:現時点で相続が発生した場合に相続人となるべき者を言います。
事例2
夫Aが死亡しました。Aには、妻B、長男C、長女Dがいましたが、Aより先にCが死亡し、Cには子Xがいます。この場合、Aが死亡すると、B、D、そしてCの代襲相続人Xが、共同相続人となります。
Aが生前、(1)Cに500万円贈与していた場合、(2) Cの死亡よりも前に、Xに対して500万円贈与していた場合、これらの贈与はそれぞれ特別受益にあたるでしょうか。
(1)代襲相続が発生した場合の被代襲者の受けた利益
代襲相続人は被代襲者と実質上同一の地位にあり,被代襲者に特別受益があれば,その直系卑属である代襲相続人(民法887条2項但書)も実質的に利益を受けていると考えられます。そこで、被代襲者の受けた贈与が、婚姻・養子縁組・生計の資本といった目的のために行われたものであれば、特別受益にあたることになります。
事例2では、Cの受けた500万円の贈与は、かかる目的のためになされたのでれば、Xに500万円の特別受益があるものとして扱われます。
(2)代襲相続人が代襲原因発生前に受けた贈与
AX間贈与契約締結時、Cはまだ死亡していないので、なおCがAの推定相続人であり、XはAの推定相続人たる地位を有しません。その為、Xへの贈与は、遺産の前渡しとは言えません。そこで、実質的に被代襲者への遺産の前渡しと評価できる特段の事情のない限り、特別受益に当たらないとした裁判例があります(福岡高判平成29・5・18判時2346-81)。この裁判例において、被相続人は自宅敷地の一部を、共同相続人に2分の1、その将来の承継人に対して2分の1を贈与していました。裁判所はこの贈与について、被代襲者たる亡き共同相続人への遺産の前渡しと評価しうる特段の事情があるとして、贈与を特別受益としました。
このように、推定相続人ではなかった者(後に代襲相続人となった者)への贈与も、その態様次第では、特段の事情があるとして、特別受益と判断される場合があります。事例2では、Xが贈与を受けた時点では、上述の通り、Xは推定相続人ではありません。もっとも、AのXに対する贈与が、Cに対する遺産の前渡しと評価できる特段の事情が認められる場合には、Xの受けた500万円が特別受益に当たる余地があります。
Q.婚約者に5000万円を贈与し、その後に結婚しました。婚約者への贈与は特別受益にあたりますか?
A. 特別受益にあたると評価される可能性が高いです。
上述の通り、贈与を受けた時点で推定相続人ではなかった場合は、贈与がされても「遺産の前渡し」とは言えず、特別受益には当たらないというのが原則です。そして、婚約者であるというだけでは、未だ婚姻が成立していない以上、「配偶者」(民法890条前段)として推定相続人たる地位を有しているとは言えません。
しかし、現在の実務では、贈与後に自分の意思で推定相続人となった場合には、特別受益と評価されることが多いです。そうでなければ、推定相続人になる前に多額の贈与を受けることで、特別受益制度を潜脱することが可能となってしまうからです。
Q. 被相続人の子が結婚し、被相続人は子の配偶者Xに贈与しました。その後、被相続人とXが養子縁組しました。Xへの贈与は特別受益にあたりますか?
A. 特別受益にあたると評価される可能性が高いです。
これについても、婚約者に贈与した後に結婚した場合と同様に考えることができ、贈与後に自分の意思で推定相続人となった場合には、特別受益として評価される可能性が高いです。被相続人の子は推定相続人(民法887条1項)ですが、子の配偶者は推定相続人ではありません。しかし、子の配偶者が、被相続人から贈与を受けた後に被相続人の養子(民法809条)となった場合は、贈与後に自分の意思で推定相続人(被相続人たる養親の子として、民法887条1項より推定相続人たる地位を取得)になったと言え、特別受益に当たると判断される可能性が高いでしょう。
贈与の時点で、将来において養子縁組することが決まっていたり、養子縁組を前提とした上で被相続人が贈与したりしたような場合には、「養子縁組のため受けた贈与」にあたるとした裁判例があります(神戸家明石支審昭和40・2・6家月17-8-48)。
Q. 被相続人が、相続人Cの配偶者Eや子Fへ財産を贈与しました。この贈与はCに対する特別受益に当たりますか?
A. 特別受益に当たる可能性があります。
特別受益の持戻しは、財産の贈与等によって直接利益を受けた者に限り認めるべきという立場が有力です。今回のケースでは、C自身が贈与を受けたわけではありません。Cは、被相続人の推定相続人ではないE・Fが贈与を受けることにより間接的に利益を受けるに過ぎない立場にあります。そこで、被相続人のE・Fに対する贈与は原則として特別受益に当たらないと考えられます。
しかし、このような間接的な受益者であっても、実質的に見ればその者が直接的に利益を受けていると評価できる場合、すなわちE・Fに対する贈与が、実質的には推定相続人たるCに対する遺産の前渡しであると評価できる場合には、Cに対する特別受益として持戻しの対象とするべきです。この点について、福島家白河支審昭和55・5・24家月33-4-75は、「贈与の経緯、贈与された者の価値、性質これにより相続人が受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められる場合には、たとえ相続人の配偶者に対してなされた贈与であつてもこれを相続人の特別受益とみて、遺産の分割をすべきである」としています。また、神戸家尼崎支審昭和47・12・28家月25-8-65は、相続人が子への扶養義務(民法877条1項 (※1))を怠ったことに起因して被相続人が相続人の子に贈与した場合についても「特別受益」に当たると判断しました。
(※1)扶養義務:一定の親族の間で、互いに生活の扶助をする義務を言います。直系血族及び兄弟姉妹は当然に扶養義務を負い(民法877条1項)、特別の事情があるときには家庭裁判所は3親等内の親族に扶養義務を負わせることができます(877条2項)。
Q.持戻しの対象となる「婚姻」のため受けた贈与とは、具体的にどのようなものですか?
A. 「婚姻」のため受けた贈与をその文言通りに解釈すると、婚姻に関連して贈与された財産は全て特別受益に該当するものとも思えます。しかし、「一般的には、通常の結納金や結婚式の挙式費用は含まれず、特別の持参金や支度金が、特別受益になる」と解されています(窪田充見『家族法 民法を学ぶ 第4版』(有斐閣 2019年) 414頁)。但し、結納金や挙式費用という名目で贈与されていれば全て特別受益に該当しない訳でもなく、共同相続人間の公平を図るという特別受益制度の趣旨に鑑み、他の相続人に贈与された財産の価格とのバランスなどから特別の利益と言えるかを実質的に判断することになります。
その為、婚姻披露宴の費用634126円や嫁入道具474250円の贈与を特別受益とした審判例(長野家審昭和57・3・12家月35-1-105)がある一方で、嫁入支度品の価格が遺産総額に比べて極めて少額であるなどの場合は、「相続分の算定にほとんど影響のないもの」として、特別受益は当たらないとしたものがあります(大阪家審昭和38・9・18家月16‐1‐137)。
従って、遺産に対して、極めて高額な贈与がされた場合には、かかる婚姻関係費用の贈与が遺産の前渡しと評価される余地もありますが、常識的な金額にとどまる場合には、扶養の範囲内として特別受益には当たらないと考えられます。
Q. 養子縁組のため」受けた贈与とは、具体的にどのようなものですか?
A. 子を養子縁組に出す際、実親が子に持参金を持たせる(贈与する)ことがあります。
実親との親子関係が解消される特別養子縁組(民法817条の2第1項)の場合、子は実親が亡くなったとしても相続人とはならないので、贈与された持参金が特別受益に当たるということもありません。
他方で、実親との親子関係を継続したままなされる普通養子縁組の場合、子は実親及び養親双方の推定相続人(民法809条、887条1項)となります。その為、実親が死亡すれば、その子は相続人となり、養子縁組の際に贈与された持参金について、特別受益に当たると考えることになります。
事例3
夫A、妻B、長男C、長女Dという家族において、長男Cが親族の養子となることが決まり、AはCに持参金として600万円を贈与しました。その半年後、Aが亡くなり、遺産として3000万円の預貯金があります。
(1)Cと親族との養子縁組が特別養子縁組である場合
CとA(及びB)との親子関係は解消されており、Aが死亡してもCはAの相続人とはなりません。従って、Cに対する贈与が特別受益に当たることはなく、Aの遺産3000万円は、BとDとで、それぞれ2分の1ずつの法定相続分(民法900条1号)に従い、1500万円ずつ相続することになります。
(2)Cと親族の養子縁組が普通養子縁組である場合
AとCの親子関係は継続していますから、Aが死亡すればCもB及びDと同じく、Aの相続人となります。それ故、AがCに持参金として贈与した600万円は特別受益となり、みなし相続財産は3000万円+600万円=3600万円となります。
この場合のB・C・Dの法定相続分はそれぞれ2分の1、4分の1、4分の1(民法900条1号、4号本文)ですから、Bは1800万円、Cは900万円、Dは900万円が、一応の相続分となります。
そして、Cはすでに相続すべき900万円のうち600万円を遺産の前渡し、すなわち特別受益として受け取っているので、実際にはAの遺産3000万円につき、Bは1800万円、Cは900万円-600万円=300万円、Dは900万円を相続する、ということになります。
Q. 持戻しの対象となる「生計の資本として」受けた贈与とは、具体的にどのようなものですか?
A. 広く生計の基礎として役立つ財産上の給付で、扶養義務の範囲を超えるものをいいます。例えば、居住用不動産の贈与や、独立した子の生計への資金援助などが典型例として挙げられます。
高等教育の学費も、被相続人の資力や社会的地位に照らして扶養義務の範囲を超えると認められる場合には、特別受益に該当します。子が複数いる場合に、一人だけ大学へ進学させた・留学させたなどの事情があっても、子の特性に応じた教育を与えることは、親の扶養義務の範囲内なので、特別受益には当たらないとされることが多いです。
私立大学医学部への入学金は、他の教育費と比べて特別に高額な為、特別受益に当たるとされることが多いです(片岡・菅野「第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」252頁、小林謙介「遺産分割事件における特別受益に関する基礎的な注的枠組みと審判例について」ケース研究326号175頁)。もっとも、被相続人たる親が開業医であり、長男に家業を継がせることを強く希望していた為に、長男だけが私立大学医学部へ進学した場合については、(親の扶養義務の範囲内の行為として)特別受益に当たらない、との判断がされた裁判例もあります(京都地判平成10・9・11判タ1008-213)。
Q. 毎月、親から決まった額の送金を受けていますが、これは特別受益に当たりますか?
A. 月の送金額が10万円を超えている場合は、「生計の資本として」の贈与に該当し特別受益に当たる、とされる可能性が高いでしょう。
生活資金の援助は、まさに「生計の資本として」受けた贈与ですが、少額であれば小遣いとして親の扶養義務の範囲内であるため、特別受益に当たらない、とされています。そして、少額かどうかの判断は、概ね10万円を基準になされています。但し、被相続人の資力や財産状態、送金を受ける側の事情なども考慮されるので、一概に、10万円以下であれば特別受益に当たらず、逆に10万円を超えていれば特別受益に当たると言い切ることはできません。
また、普段は8万円の送金を毎月受けていたが、3か月間だけ12万円の送金を受けた月があったというような場合は、12万円×3か月=36万円が特別受益となり得ます(10万円を超える分だけを計算するのではありません)(東京家審平成21・1・30家月62-9-62)。但し、心身に障害があるため働けず無収入であるなどの事情がある場合は、10万円を超える送金であっても「親族間の扶養的な金銭援助」の範囲内とされ、特別受益には当たらないと判断される可能性が高いでしょう。
Q. 相続分の譲渡は「贈与」として特別受益に当たりますか?
A. 特別受益に当たります(最判平成30・10・19民集72-5-900)。
この判例について、人物関係を分かりやすく夫A、妻B、長男C、長女Dとした上で説明します。
事例4
夫Aが亡くなり、妻B、長男C、長女Dが遺産を相続するにあたり、BはCに自らの相続分を全て譲渡し、B自身は相続の手続から外れました。
やがてBも、「全財産をCに相続させる」との遺言を残して亡くなりました。
そこで、Dが自らの相続分について請求する訴えを起こし、その中で、被相続人をAとする遺産相続時に、同じ共同相続人の地位にあったBからCへの相続分の譲渡は、特別受益としての「贈与」に当たると主張しました。
これに対し、最高裁判所は、共同相続人間の相続分の譲渡とは、「譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するもの」であり、「民法903条1項に規定する『贈与』に当たる」としました。
Q. 被相続人は生命保険に入っていました。共同相続人の一部が取得した死亡保険金は、特別受益に当たり、持戻しの対象となりますか?
A. 原則として特別受益に当たらず、持戻しの対象にはなりません。
共同相続人の1人を受取人とする死亡保険金請求権は、保険契約に基づいて、保険金受取人が固有の権利として取得するものであって、保険受取人が被相続人から承継取得する権利ではありません。それ故、死亡保険金は相続の対象にはなりませんし、「遺贈」や「贈与」(民法903条1項)にも当たらず、特別受益として持戻しの対象になることもありません(最判昭和40・2・2民集19-1-1)。
事例5
夫Aが亡くなり、妻B、長男C、長女DがAを相続することになりました。Aは生命保険に加入していて、Aの死亡保険金の受取人は、妻Bになっています。
この場合、死亡保険金について請求する権利は、BがAから相続を原因として承継したものではなく、固有の権利として有するものです。つまり、Aが、自己の相続財産をBに遺贈したり贈与したりしたものではありませんから、特別受益には当たらず、持戻しの対象にもなりません。
但し、例外として、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、民法903条の類推適用により、特別受益として持戻しの対象になるとされています(最判平成16・10・29民集58-7-1979)。そして、そのような特段の事情があるか否かは、保険金の額や保険金の遺産の総額に対する比率のほか、被相続人と同居していたか、被相続人に対し介護等でどれだけ貢献していたか、保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態、などの事情を総合考慮して判断されます。
実際に、この特段の事情を認めた裁判例(東京高決平成17・10・27家月58-5-94)があります。この事例では、相続人が受領した保険金額は合計1億129万円(1万円未満切捨)に及び、遺産の総額1億134万円(総相続財産の99.9%)に匹敵する巨額の利益を受けた場合でした。そして、受取人を当該相続人に変更したことにより保険金を受取ることになりましたが、当時相続人は被相続人と同居もしておらず、被相続人夫婦の扶養や療養介護を託するといった明確な意図のもとに保険料の受取人が変更されたと認めることも困難であるとして、他の事情と総合考慮した結果、特段の事情が存するとしました。
このように特段の事情があるとして、民法903条が類推適用されれば、特別受益に準じて持戻しの対象となります。
Q. 死亡保険金は、原則として持戻しの対象とはならないものの、例外的に、特段の事情がある場合には持戻しの対象になることが分かりました。では、特段の事情が認められた場合、何が持戻しの対象となるのでしょうか?
A. 払込総額なのか、保険金額なのかについて判断は分かれていますが、近年の裁判例では支給された保険金額を全額持戻しの対象とする判断があります。
持戻しの対象については3つの説の対立があります。①被相続人による保険料支払に着目すれば、払込総額や解約価額が持戻しの対象となります。また、②保険契約における保険契約者と保険金受取人との間の対価関係を生前贈与(民法549条)と捉えれば保険金額となります。しかし、①では共同相続人に不利に、②では保険料受取人たる相続人に不利になります。そこで、③保険契約者が死亡時までに支払った払込総額の総保険料に対する比率を保険金額に乗じた額とする説が有力とされています(前田陽一ほか『LEGAL QUEST民法Ⅳ 親族・相続(第5版)』295頁(浦野由紀子)(有斐閣、2020年))。
確かに、上記③の見解のように、「特別受益分として持戻すべき額は、保険契約者であり保険料負担者である被相続人において、その死亡時までに払い込んだ保険料の、保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額とすべきものと考える」とした審判もあります(大阪家審昭和51・11・25家月29-6-27)。この事例では、未だ保険料を殆ど支払っていなかった事例でした。支払うべき保険料の総額(166万800円)に対して支払済保険料が5万5360円であり、支給された997万2320円に、保険料総額に対する支払保険料割合を乗じると、33万2410円(少数点切捨)が持戻し対象となりました(もし①に従えば、5万5360円、②に従えば997万2320円となり、説ごとに持戻額が大きく異なることが分かります。)。
しかし、前掲の東京高裁平成17年決定では、1億129万円を特別受益に準じて持戻しました。上記で言えば②の見解を採り、保険金額を持戻しの対象としました。
以上のように、死亡保険金について、何が差戻しの対象となるかは判断が分かれていますが、近年では裁判所は②保険金額を全額持戻しの対象とする考え方を重視しているともいえるでしょう。
Q. 死亡退職金請求権は、持戻しの対象となりますか?
A. 原則として特別受益に当たらず、持戻しの対象になりません。
死亡保険金と同様、受給権者が自己固有の権利として取得するものであること(最判昭和55・11・27民集34-6-815)や、受給権者の生活保障的機能を重視(大阪家審昭和53・9・26家月31-6-33)すれば、特別受益として扱うべきではないからです。
一方で、被相続人の生前の功績に報いる形で支給される、報酬の後払的性格を重視して、共同相続人間の公平の観点から特別受益に当たると考える立場もあります(東京地判昭和55・9・19家月34-8-74)。しかし、実務上、死亡退職金が報酬の後払的性格を有するものとして特別受益に当たると認定されることは少ないようです。
Q.遺族年金は、持戻しの対象となりますか?
A. 遺族年金も受給権者の固有の権利であり、遺族年金の趣旨は受給権者の生活保障にあることから、被相続人の相続財産とすることはできないとした裁判例(大阪家審昭和59・4・11家月37-2-147)があります。
これを踏まえると、遺族年金は、受給権者が被相続人から承継取得するものではないので、特別受益としての「遺贈」や「贈与」に該当せず、持戻しの対象とはならないと考えられます。
Q. 特別受益に当たる財産から生じた果実も、特別受益に含まれますか?
A. 特別受益に含まれません。
贈与後、相続までに生じた果実(※1)については、贈与を受けた者が目的物を管理・運用したことにより生じます。すなわち、果実は遺産の前渡しという性質ではなく、目的物の管理・運用の成果物としての性質を有しています。また、特別受益の評価基準時は相続時(民法904条)です。その為、果実は特別受益には含まれません。
(※1)果実:元物(収益として果実を生じるもの)から発生する経済的利益のことを言います。りんごやぶどう、牛乳といった物の用法に従い収取する産出物を天然果実(民法88条1項)といい、建物の賃料(民法601条)などといった物の使用の対価として受けるべき金銭その他の利益を法定果実(民法88条2項)と言います。
Q. 相続人の1人が生前に被相続人から贈与を受けていましたが、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」受けた贈与ではないから、特別受益に当たらない、と主張して、他の相続人と争いになっています。このような場合はどうしたら良いでしょうか?
A. 相続人間の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の判断を仰ぐことをお勧めします。その場合には、問題となっている贈与が①’遺産の前渡しと評価されるものであること、②’他の相続人との公平性に鑑み多額であることを具体的に主張する必要があります。
Q. 相続人である私は、被相続人から賃借した土地上に建物を建てて居住しています。月々の賃料は支払っていますが、権利金は支払っていません。権利金を支払わなかったことは、特別受益に当たりますか?
A. 権利金(※1)を取引する慣行のある地域であれば、権利金相当額が特別受益に当たる可能性が高いです。
(※1)権利金:土地・家屋の賃借権の設定や譲渡に際して、賃借人側から地主・家主に対して支払われる、敷金(民法622条の2第1項柱書)以外の金銭のことを言います。権利金の支払いの要否や法的性質は、社会的慣行によって定められるため、多種多様です。
Q. 相続人である私は、被相続人が所有する(民法206条)土地を無償で借り(使用貸借:民法593条)、その上に建物を建てて居住しています。このような土地の無償利用は特別受益に当たりますか?
A. 土地の無償利用も、実務上、特別受益に当たると評価される可能性があります。
被相続人・相続人間で、「被相続人が所有する土地上に無償で建物を建てて利用してよい。」との合意があった場合、これは土地について使用貸借契約を結んだことになります。そして、使用貸借契約は贈与契約ではありませんから、一見、特別受益には当たらないように思われます。
しかし、土地上に建物が建っていると土地の価値が下がる一方、使用貸借契約を締結した相続人は、土地を無償で利用できるという利益を受けています。つまり、土地所有者である被相続人の財産が減少する一方で、相続人は利益を得ているという関係が存在し、これは被相続人が相続人に「遺贈」又は「贈与」した場合と同様の関係にあると言えます。その為、被相続人から相続人に使用貸借権の評価額の利益が無償で贈与されたのと同じであると考え、特別受益として持戻しの対象とされる傾向にあります。
因みに、使用貸借権の評価額は、土地上に建っている建物が、比較的撤去の容易な非堅固の建物(木造、軽量鉄骨)なら、土地更地価格の1~2割、堅固な建物(重量鉄骨・コンクリート造)なら、土地更地価格の2~3割、とされています。
Q. 相続人である私は、被相続人の所有する建物を無償で使用してきました。特別受益に当たりますか?
A. 建物の無償利用については、上述した土地の無償利用の場合と異なり、特別受益には当たらないと評価される可能性が高いです。
被相続人と同居していなかったことや無償で使用してきた建物の本来得るべき家賃が高額であること、建物が営業用建物であったこと等の事情も一切関係ありません。
土地の場合は、土地上に建物が建つと土地の価値が減少しますが、建物の場合は、誰かに使用させていたことで、建物の価値が減少する訳ではありません。その為、土地の場合とは異なり、被相続人が価値減少分を相続人に贈与したと考えることはできません。
Q. 「相続させる」旨の遺言による受益も、特別受益として持戻しの対象となりますか?
A. なります(最判平成3・4・19民集45-4-477)。
「長男Cに甲土地を相続させる」といった、特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を「特定財産承継遺言」(民法1014条2項参照)と言います。
そして、この特定財産承継遺言については、これが特定遺贈(民法964条)であるか遺産分割方法の指定(民法908条前段)であるかが争われてきました。この点について、判例は、「『相続させる』趣旨の遺言は、・・・遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議・・・もなし得ないのであるから、・・・何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される」と判示しています(最判平成3・4・19)。特定財産承継遺言を遺産分割方法の指定と解する場合、本判決以前の議論では、被相続人の死亡後、遺産分割が成立するまでは、財産の承継人とされた者(上述の例では、長男C)は当該財産を取得することはできず、共同相続人の共有(民法249条)に属すると考えられていました。それが、本判決により覆され、遺贈と同様、相続開始と同時に、当該財産の所有権が承継人として指定された者に移転するものと解された点がポイントです。
そこで、遺贈の場合と同様に、特定財産承継遺言による受益も特別受益として持戻しの対象になると考えられています。
事例6
夫Aが亡くなり、妻B、長男C、長女DがAの相続人となりました。Aには2000万円の相続財産があり、Aはその内「1000万円をCに相続させる」との遺言を残していました。
(1) 具体的相続分の算定
この場合、Aの相続財産2000万円の内、1000万円をCに相続(遺産分割方法の指定)させることとされているので、B・Dの相続分は、残りの1000万円を基準として算定されるとも思えます。もっとも、Cに承継される1000万円は、特定財産承継遺言による受益であり、特別受益として持戻しの対象となります。その為、B・Dの相続分を算定する上での見なし相続財産は、1000万円+1000万円(特別受益)=2000万円となります。そして、B・C・Dの法定相続分は、それぞれ2分の1(民法900条1号)、4分の1(民法900条1号、4号)、4分の1です。
よって、Cに対する特別受益が存在しなかった場合のB・C・Dの一応の相続分は、それぞれ2000万円×1/2、2000万円×1/4、2000万円×1/4で算定され、1000万円、500万円、500万円となります。そして、Aから特別受益を受領していないB・Dの具体的相続分は、一応の相続分同様、それぞれ1000万円、500万円です。一方で、Aから特別受益1000万円を受領しているCに関しては、本来の相続分から特別受益を控除したものが具体的相続分となるので、500万円(本来の相続分)−1000万円(特別受益)=−500万円がCの具体的相続分となります。
(2) 負の値を取る具体的相続分の処理方法
ここで、「特定財産承継遺言と特別受益の関係」の他に問題となるのが、具体的相続分が負の値をとった場合(一応の相続分から特別受益を控除した結果がゼロ以下となる場合)の処理方法です。事例3のように、特別受益を得た者の具体的相続分も正の値を取る場合には、特別受益に該当する財産を除いた残りの相続財産を、各共同相続人の具体的相続分に従って分配すればよく、特段の問題は生じません。他方で、特別受益を受け取った相続人の具体的相続分が、事例6のCのように負の値をとった場合について、民法は903条2項以外に手がかりらしき規定を設けておらず、解釈に委ねられています。
この点について、民法903条2項は、「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」旨規定しています。そして、かかる規定は、一般的に、Cのような相続人の相続分を0とすることを規定したに過ぎず、−500万円部分についてCが何らかの行動をとる(他の相続人たるBやDに返還する等)ことは求められていないと解されています。その為、B・Dの具体的相続分は、上述の通り、それぞれ1000万円、500万円とされていますが、Cへの特別受益を除いたAの相続財産1000万円では、両者の具体的相続分を埋め合わせるのに500万円不足することになります。
(3) 満たされない具体的相続分とB・Dの負担割合(※)
ここで、B・Dの具体的相続分の内、満たされない500万円については、上述の通りCによる返還等が予定されていない以上、B・Dの負担に帰する(B・Dの具体的相続分はその分だけ減少する)ことになりますが、さらに問題となるのがB・Dの負担割合です。
この点については、主に以下の3つの方法が考えられます(窪田充見『家族法 民法を学ぶ 第4版』(有斐閣 2019年) 425-426頁)。
①’CをいないものとしてB・Dの具体的相続分を算定する
②’法定相続分に応じて負担割合を決める
③’具体的相続分に応じて負担割合を決めるという
①’について
これは、具体的相続分の無いCを相続人でないものと同様に扱い、B・Dの具体的相続分を計算するものです。具体的には、Cが相続人であるとして、Cに対する特別受益を持ち戻したことで、具体的相続分が負の値になるという事態が発生してしまいました。そこで、Cを相続人でないものとする、すなわちCの特別受益を持ち戻すことなくB・Dの具体的相続分を計算する(それぞれの具体的相続分は、どちらも1000万円×1/2=500万円(民法900条1号))ことで、具体的相続分の値がマイナスに振れることを回避することが可能となります。但し、この見解の1番の問題は、被相続人たるAよりも前に死亡していたり、相続放棄をしたりした訳でもなく、Aの相続人たる地位を有しているCを、相続人ではないものとして扱うことに対する違和感があるという点に求められます。
②’について
これは、B・Dの法定相続分の割合に応じて、500万円の負担を分配するものです。但し、①’の見解とは異なり、Cはあくまで相続人たる地位を有するものとして扱われることになるので、Cも含めた上での法定相続分(B:2分の1、D:4分の1)をそのまま用いると、結局Cの法定相続分4分の1にあたる125万円(500万円×1/4)のマイナスが生じてしまうことは避けられません。そこで、1/2(Bの法定相続分):1/4(Dの法定相続分)=2:1であることを利用して、B・Dの負担割合を、それぞれ3分の2、3分の1とし、Bが約333万円、Dが約167万円の負担を負うものと結論づけられます。
③’について
これは、(1)における具体的相続分の計算を前提として、B・Dの負担割合を計算するものです。具体的には、B・Dの具体的相続分は併せて1500万円であり、この1500万円に占めるB・Dの具体的相続分の割合は、それぞれ3分の2(1000万円/1500万円)、3分の1(500万円/1500万円)となります。その為、B・Dの負担額は、それぞれ約333万円(500万円×2/3)、約167万円(500万円×1/3)となります。
まとめ
以上の見解をまとめると、現実にそぐわない①’を除く②’③’であれば、相続人の構成に変化を与えず妥当性を有するものと考えられます。なお、事例6では、偶然にも②’及び③’におけるB・Dの負担割合及び負担額が一致しましたが、相続財産の評価額や特別受益の価格等によっては異なる値をとることもあるので、注意が必要です。
※ 窪田充見『家族法 民法を学ぶ 第4版』(有斐閣 2019年) 424-426頁 参照
Q. 特別受益に該当するためには、贈与の期間制限等はありますか?
A. ありません。(1)被相続人から相続人に対してされた、(2)①遺贈、②婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与、③特定財産承継遺言で相続した財産のいずれかにあたるのであれば、何年前にされた贈与であっても特別受益に当たります。
なお、遺留分算定のための財産の価格を計算するにあたっては、原則として相続開始前1年間になされた贈与に限り算入され(民法1044条1項)、相続人に対する贈与の場合には、相続開始前10年間になされたもの(民法1044条3項前段)で、且つその贈与が「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」(民法1044条3項後段)であるもののみが算入されます。
Q. 特別受益は、必ず相続財産に加えて計算しなくてはいけないのですか?
A. 被相続人が遺贈又は贈与を行うにあたって持戻しを免除する旨の意思表示をした場合には、被相続人の意思を尊重し、共同相続人の具体的相続分を算出するに際して、当該遺贈又は贈与は特別受益に該当するものの、持戻しの対象からは除外されます(民法903条3項)。
また、そのような持戻し免除の意思表示が存在しない場合であっても、「婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について」持戻し免除の意思表示を行ったものと推定されます(民法903条4項)。これは、婚姻期間が20年以上ある夫婦の間における居住用建物の贈与等は、その一方の死亡によっても他方の生活が守られること(他方配偶者の生活保障)を企図してなされることが多い点に鑑みた規定であると言えます。
事例7
夫Aが高齢で亡くなりました。Aは遺言で、長年連れ添った同じく高齢の妻Bに対し、Bが今後も安心して暮らせるよう、夫婦で共に住んでいたマイホームとその敷地(併せて評価額2000万円)を贈与しました。Aの共同相続人にはBのほか、長男Cと長女Dがいます。また、Aには他に4000万円の金融財産が有ります。
この場合、AB間で行われたAの遺贈は特別受益として原則持戻しの対象になります。そして、仮に持戻し免除の意思表示が無かったとすると、原則通り持ち戻されるので、2000万円の不動産と4000万円の金融財産の計6000万円をB、C、Dの3人で分け合うことになります。その為、法定相続分が2分の1(民法900条1項)であるBは、その内3000万円相当の財産を相続することができますが、これでは、2000万円の不動産の他、1000万円の金融財産しかBは相続できないことになります。
一方で、A及びBの婚姻期間が20年を超える場合は、Bに遺贈された2000万円の居住用不動産は持戻しの対象とはならないので、残りのAの相続財産たる金融財産4000万円をB,C,Dの3人で分け合うことになります。その為、法定相続分が2分の1であるBは、2000万円の居住用不動産の他に、2000万円の金融財産を相続することができます。
以上より、民法903条4項の推定規定が存在することで、Bは、持戻し免除の意思表示がない(推定されない)場合と比べて1000万円多い財産を得られることになり、その分Aの死後におけるBの生活が保障されることとなります。
Q. 「推定する」(民法903条4項)とは、どういうことでしょうか?
A. 端的には、遺産分割の協議が調わず、裁判で争うこととなった場合(民法907条2項本文)や、遺留分侵害額請求が裁判上でなされた場合などに、裁判上での立証責任(挙証責任 (※1))が転換されるということを意味します。
本来ならば持戻し免除の意思表示が存在することで利益を受ける被相続人の配偶者がその存在を立証する責任を負い、これを立証できなければ、持戻し免除の意思表示は無かったものとして、持戻しの対象とされてしまいます。しかし、民法903条4項は、配偶者による立証がなくても、同項所定の居住用財産の贈与については持戻し免除があったものとしてひとまず扱い、これを覆す事情について、持戻し免除の意思表示の存在を争う他の相続人の側に負わせることとしているのです。
(※1)立証責任(挙証責任):証明の対象となる事項について、当事者の努力等にも関わらず、裁判所がその存否を確定できない場合に、裁判所がその事実の存在又は不存在を擬制して法律効果の発生又は不発生を判断することで当事者の一方に生じる不利益のこと。
Q. いつの時点で婚姻期間が20年以上であれば良いのでしょうか?
A. この点について、民法903条4項は、「婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人がが、・・・遺贈又は贈与をしたときは」と規定しているので、遺贈又は贈与が行われた時点を基準として、婚姻期間を算定するものと考えられます。その為、例えば、他方配偶者が被相続人から婚姻後18年が経過した段階で居住用不動産の贈与を受けた後、婚姻後23年の時点で被相続人が死亡したという場合には、贈与がなされた時点では未だ婚姻期間が20年以上ではないので、当然には持戻し免除の推定が働きません。
但し、一定の場合には、民法903条4項が類推適用される可能性は否定できません。
Q. 特別受益の評価基準時はいつですか?
A. 特別受益の金額は、遺贈の場合は相続時の評価額によります。
これに対して、贈与の場合は、受贈当時のまま相続開始時に存在するものとして評価額を算定します(民法904条)。具体的には、受贈者の行為によって、受贈後相続開始前に財産が滅失したり、価値の増減があったりしても、そのような影響は考慮せず、あくまで原状(受贈当時の状況)のまま財産が存在するとみなして評価額を算定することになります。
例えば、父Aが生前、長男Cに時価5000万円の甲土地を贈与し、A死亡時には甲土地の価額が1億円に値上がりしていた場合でも、贈与を受けた時点における原状たる時価5000万円がCの特別受益財産となります。また、Cが相続よりも前にかかる甲土地を売却してしまったとしても、これでCの特別受益が消滅することにはならず、Cの特別受益額は5000万円のままであると評価することになります。
但し、受贈者の行為によらない(不可抗力による)滅失や価格の増減については、民法904条が「受贈者の行為によって、・・・財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、・・・」と規定していることから、同条の適用はありません。滅失については特別受益がなかったものとして扱われ、価格の増減については相続開始時点における増減後の財産価格が特別受益額として算定されます。もっとも、不可抗力による滅失の場合でも、受贈者がその財産の価値的代償を得ている場合には、その代償について特別受益があることになります。
3. 持戻し免除の意思表示
Q. 持戻し免除の意思表示はどのように行えばよいのですか?
A. 決まった形式は定められていません。従って、明示的な意思表示のほか、黙示的な意思表示であっても認められます。
但し、持戻し免除の意思表示は、その有無が相続財産の計算において直接に影響するものであるため、被相続人の死後、共同相続人間での争いの種となることが予想されます。その為、持戻し免除の意思表示を行ったことにつき、書面で明確に残しておくべきでしょう。具体的には、贈与契約の際、契約書に持戻しを免除する旨記載しておく、公正証書遺言(民法969条)で持戻し免除の意思表示を行っておく等の方法が考えられます。
Q. 持戻し免除の黙示の意思表示があったとされるのは、如何なる場合でしょうか?
A. 持戻し免除の黙示の意思表示があったとされるのは、①意思表示があったと認めることが衡平であり、②認めることが被相続人の合理的意思も合致する場合です。そして、これらの要件を満たすかは、遺言の文言、贈与の内容・価額・動機、被相続人と受贈者の関係・他の相続人への贈与の有無、その内容及び価額、など個別具体的な事情を総合考慮して判断されます。
実際に、様々な事情を総合考慮して持戻し免除の黙示の意思表示があったとした裁判例(東京高決平成21・12・18判タ1330-203)があります。この裁判例では「生計の資本として贈与を受けた」(民法903条1項)ものであることを否定した上で、仮に生計の資本とした場合でも、公正証書遺言の文言、全相続人の年齢、稼働能力、居住生活、問題となった不動産の所在地・種類等、受贈者のみに遺産の一部を承継させた意味等を考慮し、持戻し免除の黙示の意思表示が包含されていると判断しました。
また、受贈者である妻の長年にわたる貢献に報い、その後の老後の生活の安定を図るために行われたこと、受贈者に他に老後の生活を支えるに足りる資産もないこと、贈与時の贈与当事者の年齢や収入等を考慮して、持戻し免除の黙示の意思表示があったとした裁判例(東京高決平成8・8・26家月49-4-52)もあります。
4. 特別受益と遺留分
Q. 特別受益と遺留分侵害額請求権(民法1046条1項)との関係はどのようなものでしょうか?
A. 特別受益は、各共同相続人の具体的相続分を算定する場面において、共同相続人間の公平を確保するために問題となるものです。これに対し、遺留分侵害額請求権(※1・※2)の行使は、被相続人による財産の処分によって、相続人が法の保護する最低限の相続分も受け取れないという場合に登場するものです。その為、両者は直接関係を有するとは言えません。
しかし、遺留分制度の趣旨は、上述の通り、相続人に最低限の相続分を保障する点にあります。そして、被相続人が特別受益に当たる贈与について持戻し免除の意思表示をしていた場合であっても、その贈与財産を遺留分侵害額の算定の基礎となる財産の額からも除外することは、相続人に最低限の相続分を保障したことになりません。
従って、遺留分侵害額請求権が行使された場合、具体的相続分の算定にあたって持戻しを免除された特別受益であっても、遺留分侵害額算定の基礎となる財産の算定にあたっては、当然に算入の対象となります(最決平成24・1・26家月64-7-100)。この場合、持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する範囲でその効力を喪失します。かかる判例の立場は改正民法1044条3項に明文化されました。
事例8
夫Aが亡くなり、妻B、長男C、長女Dがいたとします。Bは相続を放棄した(民法938条)ので、Aの相続人はCとDのみ(民法939条・887条1項)です。
そして、Aは亡くなる半年前、Cに対し、唯一の財産である4000万円の預貯金を贈与していました。
この場合、Aが持戻し免除の意思表示をしていなかったなら、4000万円の贈与は持戻しの対象となり、CとDによる遺産分割の対象となります。結果、C及びDの一応の相続分は、いずれも2000万円(民法900条4号)となり、Cについては、特別受益の4000万円を差し引き、具体的相続分は0となります(Dにつき、具体的相続分も2000万円)。
これに対し、Aが持戻し免除の意思表示をしていれば、4000万円は遺産分割の対象となりません。そして、他にAの相続財産は無い以上、このままではDは何も相続することができず、Dの遺留分は侵害されることになります。
もっとも、持戻し免除の意思表示の有無に関わらず、4000万円は遺留分侵害額算定の基礎となる財産には含まれます。そうすると、Dの遺留分は相続財産の4分の1ですから(民法1042条1項2号、2項)、DはCに対して1000万円(4000万円×1/4)を請求することができます。
(※1)遺留分:遺言の内容に関わらず、法定相続人については最低限の遺産取得分を保障する、その取得分のこと(民法1042条以下)を言います。
(※2)遺留分侵害額請求権:かかる遺留分を侵害された場合に、侵害額に相当する金銭を請求できる権利を言います。
Q. 特別受益と中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号、以下「経営承継円滑化法」)の関係はどのようなものでしょうか?
A. 経営承継円滑化法は、遺留分に関する民法の特例について定めている法律です。企業の後継者が、遺留分に関して以下のような特例の適用を受けることができるように規定を設けています。
但し、遺留分権利者全員との合意および所要の手続き(経済産業大臣の認定や家庭裁判所の許可等)を経ることが必要です(経営承継円滑化法7条、8条)。
①固定合意(経営承継円滑化法4条1項2号)
遺留分算定の基礎となる財産の算定に際して、遺贈又は贈与を受けた財産(株式)の持戻し価額を、合意時点における評価額をすること旨合意すること。
②除外合意(経営承継円滑化法4条1項1号)
遺贈又は贈与を受けた財産(株式)を、遺留分算定の基礎となる財産から除外する旨合意すること。これにより、原則として持戻しが免除されないはずの遺留分算定の基礎となる財産の算定にあたっても、特別受益が例外的に持戻しの対象から除外されることになります。
経営承継円滑化法は、遺留分について定められた法の1つです。そして、上述の通り、特別受益制度と遺留分制度は直接の関係があるものではありません。その為、特別受益と経営承継円滑化法も、直接の関係はありません。
つまり、経営承継円滑化法の除外合意や固定合意と、特別受益の持戻し免除の意思表示は、別個独立の制度として規定されています。
従って、除外合意された財産でも特別受益に該当するのであれば、具体的相続分の算定にあたっては持戻しの対象となりますし、また、固定合意された財産でも特別受益に該当するのであれば、具体的相続分の算定にあたっては、相続開始時が持戻しの際の評価基準時となります。これを回避したい場合には、除外合意・固定合意を行った場合でも、別途、具体的相続分の算定にあたって持戻し免除の意思表示を行っておく必要があるということに注意が必要です。
5. おわりに
これまで見てきたように、特別受益については、その制度内容を把握していないと、持戻しや遺留分侵害を理由に不利益を被ることになる可能性があります。他方で、特別受益を受けられなかった他の相続人は、併せて遺留分侵害額請求権についても把握しておかなければ、特別受益による侵害額相当の不利益を甘受しなければならないことにもなりかねません。相続手続にあたっては、十分にご注意いただければと思います。ご不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡ください。