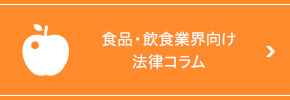寄与分Q&A
Contents
- 1 はじめに
- 2 寄与分の概要
- 2.1 Q.寄与分とは何ですか?
- 2.2 Q.具体的に、どのような寄与が、寄与分と認定されるための要件を備えていると言えるのでしょうか?
- 2.3 Q.寄与分はどのようにして決められるのですか?
- 2.4 Q.寄与分について家庭裁判所に寄与分の定めを請求する場合(民法904条の2第2項)の流れはどうなっているのでしょうか?
- 2.5 Q.共同相続人以外の者が行った寄与は、寄与分として評価されますか?
- 2.6 Q.代襲相続(民法887条2項、3項)(※7)の場合は、寄与分の扱いはどのようになりますか?
- 2.7 Q.配偶者の財産の維持・増加に寄与してきましたが、その後に離婚(民法728条1項)しました。離婚後にその元配偶者が死亡しましたが、寄与分は認められますか?
- 2.8 Q.包括受遺者(民法964条)がいる場合、この者の寄与分は認められますか?
- 2.9 Q.被相続人が遺言(民法960条以下)で寄与分を定めていた場合は、どのように扱えばよいのですか
- 2.10 Q.共同相続人の中に、客観的に見て「被相続人の財産の維持又は増加」に貢献した者が複数人います。しかし、その中でも寄与分について主張する者(ここでは「X」とする)と、しない者(ここでは「Y」とする)とがいるのですが、どのように扱うべきでしょうか?
- 2.11 Q.寄与分はいつまでに主張すべきなのでしょうか?
- 2.12 Q.寄与分は如何なる基準に基づいて算定されるのでしょうか?
- 2.13 Q.特別の寄与をした相続人自身は被相続人から贈与等を受けたことはないのですが、当該相続人の配偶者や子は、生前の被相続人から贈与を受けていました。寄与分の算定にあたり、何か影響がありますか?
- 2.14 Q.寄与分の額に何か制限がありますか?
- 2.15 Q.寄与分を定めた結果、他の相続人の遺留分(民法1042条)を侵害することになってしまいました。このような寄与分の定め方も可能なのでしょうか?
- 2.16 Q.寄与分を請求する権利があることについて、訴訟で確認してもらうことはできますか?
- 2.17 Q.寄与分について他の手段により請求できませんか?
- 2.18 Q.寄与分を他に譲渡したり、他者の有する寄与分を代わりに主張したりすることはできますか?
- 3 寄与分と具体的相続分
- 4 特別寄与制度
- 4.1 Q.民法改正により導入された特別寄与制度(民法1050条1項)とはどういうものでしょうか?
- 4.2 Q.被相続人から寄与に対する対価の支払いを受けている場合でも、特別寄与料の請求はできますか?
- 4.3 Q.特別寄与料の請求と相続とは、どのような関係にあるのでしょうか?
- 4.4 Q.被相続人が遺言で「特別の寄与があったとは認めない」或いは「特別寄与料は○○円とする」などとしていた場合、どのように扱うべきなのでしょうか?
- 4.5 Q.特別寄与料の請求権があることについて、訴訟で確認してもらうことはできますか?
- 4.6 Q.被相続人の親族とは、具体的にどのような者を指すのでしょうか?
- 4.7 Q.特別寄与者として認められる寄与とは、どの程度のものを指すのでしょうか?
- 4.8 Q.「特別寄与料」の額は、どのように決めるのでしょうか?
- 4.9 Q.家庭裁判所の審判を待っていたのでは不安です。「特別寄与料」の仮差押(※22)、仮処分(※23)の申立てを行うことはできるのでしょうか?
- 4.10 Q.「特別寄与料」の請求について、期間制限はありますか?
- 4.11 Q.内縁配偶者やパートナーシップ制度によるパートナーなどは、「特別寄与者」になりえますか。
はじめに
特別受益制度(民法903条1項)(※1)と並んで、共同相続人(※2)間の公平を図る制度として寄与分制度(民法904条の2第1項)が存在します。
そこで、本ページでは、寄与分について、Q&A形式で説明させていただきます。
※1 特別受益:共同相続人のうち、被相続人(亡くなった方)から、遺贈(民法964条)や「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」贈与(民法549条、554条)を受けた共同相続人がいる場合、当該遺贈や贈与によって得た利益のこと。
※2 共同相続人:相続人が複数いる場合、遺言や相続人間での話し合い(遺産分割協議)に従って遺産が分割されるまで、遺産はそれらの相続人らの共有状態にあるとされます(=共同相続:民法898条)。そして、このように遺産分割前の状態における相続人らを「共同相続人」といいます。
なお、特別受益制度については、特別受益Q&A をご参照ください。
寄与分の概要
Q.寄与分とは何ですか?
A. 共同相続人の中に、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」(民法904条の2第1項)によって、「被相続人の財産の維持又は増加」について「特別の寄与」をした方がいたとします。そのような場合に、その寄与を評価し、その方に対して遺産の中から特別の金額が与えられる、或いは遺産の相続割合が特別の割合とされることがあります。
そのような特別の金額ないしは特別の割合のことを、寄与分と言います。
Q.具体的に、どのような寄与が、寄与分と認定されるための要件を備えていると言えるのでしょうか?
A. 民法904条の2第1項によれば、寄与分と認定されるには、
①寄与が「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」で行われたこと
②それが、「被相続人の財産の維持又は増加」に向けられたものであること
③それが、「特別の寄与」と言えること
という、3つの要件を満たしていることを要します。
そこで、上記①〜③について、以下、具体的な検討を加えていきます。
⑴ 寄与の態様(①)について
上述の通り、民法は、被相続人の事業に関する労務の提供・被相続人の事業に関する財産上の給付・被相続人の療養看護を、寄与の態様として例示しています。
この内、被相続人の療養看護について、高松高決昭和48・11・7家月26-5-75は、「寄与配偶者の遺産中に占める潜在的な持分は、相続分の形で定型化されているものと考えられるので、一般的な寄与をしたことを根拠として、寄与配偶者に対し法定の相続分以上の遺産を取得させることはできない」と判示しました。このことは、③の「特別の寄与」に関する議論と重なるようですが、通常の療養看護以上に特別な貢献が必要であることを指摘したものと考えられます。
また、民法は、寄与の態様として上記3つの場面の他、「その他の方法」による場合も規定しています。すなわち、「被相続人の財産の維持又は増加」に向けられた「特別の寄与」であれば、いかなる態様であっても寄与分として評価される可能性があります。「その他の方法」の例としては、被相続人の扶養・財産管理・事業に関係のない財産上の給付(被相続人が自宅を建て替えるにあたり資金を一部負担するなど)が挙げられます。
⑵ 「被相続人の財産の維持又は増加」(②)について
「特別の寄与」と「被相続人の財産の維持又は増加」との間に因果関係が認められなければ、寄与分として評価されることはありません。例えば、共同相続人の一人が通常の寄与の程度を超えた療養看護をした結果、被相続人の財産から支出されるはずだった療養看護の費用が抑えられたということであれば、「被相続人の財産の維持又は増加」と関係のある寄与と言える為、寄与分として認定される可能性があります。
また、「被相続人の財産の維持又は増加」には、共同相続人が事業の経費を代わりに支払った為、被相続人がその支払いを免れた場合など、財産の減少を防止した場合も含みます。そして、寄与によって一時的に維持されたり増加したりした財産がその後に減少してしまっても、寄与がなければさらに減少していたといえる場合であれば、寄与分が認められる可能性があります。
更に、被相続人が経営する会社への労務提供や出資は、一人会社である場合など会社と被相続人が一体であると言えるような特段の事情が存在しない限り、会社そのものは「被相続人の」財産ではない為、寄与分の対象とはなりません。しかし、被相続人が事業を行っており、共同相続人の一人が通常の寄与の程度を超えて被相続人の事業を支え、経営の悪化を食い止めたような場合は、寄与分の対象となる余地があります。
⑶ 「特別の寄与」(③)について
被相続人・相続人間には、婚姻関係や親子関係が存在することが多く、夫婦間の協力扶助義務(民法752条)や、直系血族・兄弟姉妹間の扶養義務(民法877条1項)が認められるのが通常です。その為、「特別の寄与」とは、このような被相続人との身分関係に基づいて通常期待される扶養義務の程度を超える特別の貢献を意味するものと解されます。そして、「特別の寄与」に当たるか否かは、以下の2つの点に注目して判断されます。
・共同相続人がその寄与に対する相応の対価・補償を受けていない(無償性)か。
・被相続人との身分関係において通常期待される程度を超えるものであるか。
(「寄与行為が相当期間に及び(継続性)、専従性があるか」という事情も考慮要素になり得ます。)
⑷寄与の時期
寄与分は、相続開始時(被相続人の死亡時:民法882条)までになされた寄与行為が対象です(東京高決昭和57・3・16家月35-7-55)。
Q.寄与分はどのようにして決められるのですか?
A. 原則として共同相続人間の協議で決めます(民法904条の2第1項)。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、寄与をした者の請求により、家庭裁判所の調停や審判で定めることができます(民法904条の2第2項)。
Q.寄与分について家庭裁判所に寄与分の定めを請求する場合(民法904条の2第2項)の流れはどうなっているのでしょうか?
A. 家庭裁判所に請求する前に、まずは遺産分割協議(民法907条1項)の中で、共同相続人間で寄与分に関する協議を行うことが原則です(民法904条の2第1項)。
そして、かかる協議が調わない、又は協議をすることができない場合には、上述の通り、寄与分を主張する者が家庭裁判所に対して、寄与分を定めるよう請求することができます。
この点について、家庭裁判所における寄与分を定める手続は、以下の2段階で構成されています。
①’寄与分を定める処分調停(家事事件手続法別表第二第14項)
共同相続人間で協議が調わなかった場合、又は協議ができなかった場合に、最初に申し立てることになるのが、この処分調停です。そして、「調停」とは、裁判のように勝敗を決定するのではなく、話し合いを通じて当事者相互が合意をすることにより、紛争を解決する手続です。
調停では、裁判官及び民間人から選抜された調停委員によって構成された調停委員会が、当事者双方の言い分を聴取し、双方が納得した上での合意による解決を導けるよう、助言等を行います。
②’寄与分を定める家事審判
上記処分調停によっても、共同相続人間で合意が形成されない場合、寄与分を定める審判手続の申立てを行うことになります(但し、遺産分割審判の申立ても行わないと、不適法として却下されてしまうので、注意が必要です)。
こちらの手続は、処分調停が当事者による自主的な紛争解決を促進するものであったのに対し、当事者から提出された書類等に基づいて、家庭裁判所の裁判官が寄与分に関する判断を下すものであり、当事者による合意形成を必ずしもその目的としません。
そして、②’の家事審判の内容について不服のある当事者は、当該審判について即時抗告を申し立てることができます(家事事件手続法85条1項)。
Q.共同相続人以外の者が行った寄与は、寄与分として評価されますか?
A. 原則として、寄与分としては評価されません。民法904条の2第1項が「共同相続人中に、・・・特別の寄与をした者があるときは」と規定しているように、寄与分として評価され得るのは、共同相続人が行った寄与だけです。
もっとも、共同相続人の配偶者や子が被相続人の財産の維持又は増加について寄与した場合、これらの者をその相続人の履行補助者と見て、その寄与が相続人の寄与分として考慮される可能性はあります(東京家審平成12・3・8家月52-8-35)。
また、被相続人の、相続人でない親族(※3)による寄与であれば、後述する特別寄与者(民法1050条1項)の制度により、相続人に対する寄与に応じた金銭(特別寄与料)の支払請求が認められる可能性があります。但し、例えば被相続人の内縁配偶者が、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたという場合、内縁夫婦間の相続権は認められておらず、親族にも含まれないので、かかる特別寄与分の制度によっても救済されないことになります。このような場合には、被相続人が、生前に内縁配偶者に自己の財産を贈与しておくか、遺言により財産を承継(遺贈)することで対処することが考えられます(この場合、原則として相続開始前1年以内の生前贈与は、遺留分(※4)算定の基礎となる財産の価格に算入される(民法1044条1項前段)ため、注意が必要です)。内縁配偶者及びパートナーシップ制度によるパートナーによる寄与については、「4. 特別寄与制度」のところで再度扱います。
※3 親族:民法725条は、親族の範囲を、「六親等内の血族(※5)」(1号)・「配偶者」(2号)・「三親等内の姻族(※6)」(3号)に限定しています。
※4 遺留分:被相続人の遺言の内容にかかわらず、兄弟姉妹以外の法定相続人は、法律上最低限の遺産取得分を保障されており(民法1042条1項)、この取得分を「遺留分」と言います。
そして、これが侵害されている場合、侵害を受けた相続人は、その原因となった贈与や遺贈を受けた者に対して、侵害額相当の金銭の支払いを請求することができます(1046条1項)。
※5 血族:法的親子関係の連鎖で繋がる者のこと。出生により血縁関係を有する者に限らず、養子縁組で血縁関係が擬制される場合(民法727条)も含みます。
※6 姻族:自己の配偶者の血族及び自己の血族の配偶者のこと。
事例1
夫A、妻B、長男C、Cの妻D、孫(CD間の子)Eがいました。Aが亡くなり、BとCが相続人となりました(民法890条前段、887条1項)。Aの生前、DとEがAの介護を担い、そのことによりAの財産が維持・増加していました。
この場合、DとEはAの相続人ではないため、寄与分は原則として認められないことになります。そこで従来は、DとEは相続人であるCの補助者として寄与したのだと考え、DとEの貢献をCの寄与分として考慮する、という方法が採用されていました。
この点について、平成30年の民法(相続法)改正において創設され、令和元年(2019年)7月1日より施行された特別寄与制度は、事例1のような場合において、D及びEを「特別寄与者」とし、相続人たるB又はCに対して寄与に応じた金銭の請求を行うことを認めています。但し、特別寄与制度が創設されたことで、従前の判例実務における上述の扱い(履行補助者構成)が用いられなくなるのか、両者が併存し得るのかは判然としていません。
Q.代襲相続(民法887条2項、3項)(※7)の場合は、寄与分の扱いはどのようになりますか?
A. 代襲相続においても、上述のような履行補助者構成が判例では用いられています。この点について、東京高決平成元・12・28家月42-8-45は、「共同相続人間の衡平を図る見地からすれば、被代襲者の寄与に基づき代襲相続人に寄与分を認めることも、相続人の配偶者ないし母親の寄与が相続人の寄与と同視できる場合には相続人の寄与分として考慮することも許される」と判示しています。
その為、被代襲者の死亡による代襲相続の場合、代襲相続人が、被代襲者の寄与を自己の寄与分として主張することは認められる可能性があります(東京高決平成元・12・28家月42-8-45、横浜家審平成6・7・27家月47-8-72)。
他方で、被代襲者の相続欠格(民法891条各号)や相続人の廃除(民法892条、893条)を原因とする代襲相続の場合は、代襲相続人が、被代襲者の寄与を自己の寄与分として主張することは許されないという立場も有力です。相続欠格や相続人の廃除は、被代襲者の相続分を失わせるものであり、相続分を失った者に対して相続分に修正を加える寄与分を適用することは不合理だからです。
また、代襲相続人自身の寄与については、その寄与が代襲原因発生の前後のいずれで行われたかを問わず、自己の寄与分として主張することが認められ易いです。民法904条の2第1項は寄与行為をした時点で相続人であることを要求していないことなどがその理由として挙げられます。
※7 代襲相続(人):被相続人の子(ここでは「a」とする)が被相続人より先に死亡していた場合や、相続欠格(民法891条各号)(※8)・廃除(民法892条、893条)(※9)により相続権を失っていた場合において、aの子(被相続人の孫)で、被相続人の直系卑属(※10)である者(ここでは「b」とする、民法887条2項但書)が、aの受けるはずだった相続分を、被相続人から直接に相続することを「代襲相続」といい、代襲相続するbを「代襲相続人」、代襲相続されるaを「被代襲者」といいます。また、代襲相続するbが被相続人より前に死亡していた場合や、相続欠格・廃除により代襲相続権を失っていた場合は、曾孫による再代襲も認められます(民法887条3項、887条2項)。
※8 相続欠格:本来であれば相続人となる者が、民法891条各号に規定された一定の重大な非行を行うことで、法律上当然に相続資格を喪失すること。
※9 (推定相続人(※11)の)廃除:遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して一定の非行を行った場合に、当該推定相続人の相続資格を剥奪するよう、被相続人が家庭裁判所に請求すること。
※10 直系卑属:「卑属」とは、被相続人よりも後の世代の血族のことを言います。つまり「直系卑属」とは、子、孫などを指します。なお、被相続人の養子に、養子縁組前に出生した子(被相続人から見ると義理の孫)がいる場合で、養子単独での養子縁組だった場合、その養子の子は被相続人の血族ではないため、被相続人の直系卑属に当たらず、代襲相続人にはなりません。
※11 推定相続人:相続が開始された場合、相続人たる地位を取得する者のこと。
事例2
Aが死亡しました。Aには、妻B、長男C、長女Dがいましたが、Aより先にCが死亡し、Cには子Eがいます。
この場合、Aが死亡すると、B、D、E(Cの代襲相続人)が、共同相続人となります。
(Ⅰ)CがAに生前特別の寄与をしていた場合、
(Ⅱ) Cの死亡よりも前に、Eが特別の寄与をしていた場合、寄与分の扱いはどのようになるでしょうか。
(Ⅰ)被代襲者たるCの寄与が、代襲相続人たるEの寄与分として認められる可能性はあります。
(Ⅱ)Cの生前は、CがAの子として推定相続人の地位(民法887条1項)にあり、Eは代襲相続人としての推定相続人たる地位を有しない。その為、推定相続人でないEがAに特別の寄与を行っていても、Eの寄与分として認められないとも思えます。
もっとも、上述の通り、民法904条の2第1項は、「共同相続人中に、・・・特別の寄与をした者があるときは」と規定するのみであって、特別の寄与を行った時点で相続人なくても、相続開始時点で相続人たる地位を有していれば良いと解釈されます。このような解釈に基づけば、推定相続人たる地位を有しない時期にEが行ったAに対する特別の寄与も、Eの寄与分として認めることができます。
Q.配偶者の財産の維持・増加に寄与してきましたが、その後に離婚(民法728条1項)しました。離婚後にその元配偶者が死亡しましたが、寄与分は認められますか?
A.認められません。
寄与分が認められる相続人とは、被相続人死亡時(相続開始時:民法882条)における相続人です。寄与行為の時点で配偶者、すなわち推定相続人(民法890条前段)であったとしても、その後に離婚した場合は、被相続人たる元配偶者の推定相続人ではなくなります。その為、仮に離婚後に元配偶者が死亡したとしても、過去の寄与行為を理由に寄与分が認められるということはありません。
また、特別寄与制度に関しても同様の結論が導かれることになります。具体的には、「配偶者」(民法725条2号)は「血族」(民法725条1号)にも「姻族」(民法725条3号)にも含まれないところ、離婚によりその「配偶者」たる地位を喪失すれば、被相続人たる元配偶者との親族関係は失われます。その為、「寄与をした被相続人の親族」(民法1050条1項)に該当せず、特別寄与料の請求権も認められません。
Q.包括受遺者(民法964条)がいる場合、この者の寄与分は認められますか?
A. 相続人以外の者が包括受遺者となった場合、「共同相続人」(民法904条の2第1項)には含まれないので、寄与分は認められません。この場合、当該受遺者が、「被相続人の親族」(民法1050条1項)であれば、相続人に対する特別寄与料の請求権が認められる余地はあります。
一方で、相続人が包括受遺者となった場合、「共同相続人」に含まれるので、「被相続人の財産の維持又は増加」に向けた「特別の寄与」を行っていれば、寄与分が認められます。但し、遺贈については、その目的を問わず特別受益として持戻しの対象となってしまいます(民法903条1項)。その為、持戻し免除の意思表示(黙示でも可:民法903条3項)がなければ、上述の通り、寄与分の清算があったものとして寄与分が0とされる、或いは寄与分の価格から特別受益の価格を控除した残額が寄与分として認められることになるものと考えられます。
Q.被相続人が遺言(民法960条以下)で寄与分を定めていた場合は、どのように扱えばよいのですか
A. 寄与分は、遺言で定めることができる事項に含まれない為、被相続人が遺言で寄与分について定めていたとしても、その部分は無効なものとして扱われます。
なお、遺言で定めることができる代表的な事項には以下のようなものがあります。
・認知(民法781条2項)(※12)
・相続分の指定(民法902条)
・持戻し免除の意思表示(民法903条3項)
・包括遺贈及び特定遺贈(民法964条)
・遺言執行者の指定およびその委託(民法1006条1項)
※12 認知:非嫡出子について、その父又は母との間に、意思表示又は裁判により親子関係を発生させる制度のこと。
Q.共同相続人の中に、客観的に見て「被相続人の財産の維持又は増加」に貢献した者が複数人います。しかし、その中でも寄与分について主張する者(ここでは「X」とする)と、しない者(ここでは「Y」とする)とがいるのですが、どのように扱うべきでしょうか?
A. そのような場合、Xに限って、「被相続人の財産の維持又は増加」への貢献の程度を検討し、「特別の寄与」に当たると評価できるのであれば、Xについてのみ、寄与分を認定するべきである(Yについては、仮に「特別の寄与」を行っていたとしても、これを主張しない以上、寄与分の認定を行わない)と考えられます。
Q.寄与分はいつまでに主張すべきなのでしょうか?
A. 寄与分の主張は、遺産分割手続(民法907条1項、2項)の中でしなければなりません。遺産分割後の寄与分の主張は認められません。ただし、例外として、死後認知者(※13)が価額支払請求(民法910条)をしてきたときは、寄与分の主張が認められます(民法904条の2第4項)。
※13 死後認知:被相続人が遺言で認知(民法779条、781条2項)を行ったり、相続開始後3年以内(民法787条但書)に、嫡出子でない子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人が認知の訴え(民法787条本文)を提起したりしたことで、出生の時から認知した被相続人と親子関係にあった(民法784条本文)ことになり、被相続人の相続人たる身分を取得(民法887条)します。
Q.寄与分は如何なる基準に基づいて算定されるのでしょうか?
A. 共同相続人間で寄与分の認定に関する協議が調わない場合、寄与した者の請求により、上述の通り家庭裁判所が、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して」定めることになります(民法904条の2第2項)。その他、共同相続人の数、相続債務の額、遺産分割の結果の妥当性、各共同相続人の受けた贈与や遺贈の額なども考慮の対象となります。
ここで注意しなければならないのが、寄与した者が、寄与の対価として贈与等(特別受益:民法903条1項)を受けている場合には、実質的に寄与に対する清算がなされているとして寄与分が認められない場合があるということです。寄与分0との認定を受けなくとも、寄与分額から当該贈与等の価格を差し引いた残額が寄与分とされることも考えられます。但し、当該贈与等は、「特別の寄与」に報いるためになされたものとして、持戻し免除(民法903条3項)(※14)の意思表示が推認されると考えられています(東京高決平成8・8・26家月49-4-52)。
※14 持戻し免除:具体的相続分(※15)の算定にあたり、特別受益の相続財産への持戻し(加算)をさせないこと。
※15 具体的相続分:最終的な遺産分割(民法907条1項、2項本文)の前提となる相続分のこと。
Q.特別の寄与をした相続人自身は被相続人から贈与等を受けたことはないのですが、当該相続人の配偶者や子は、生前の被相続人から贈与を受けていました。寄与分の算定にあたり、何か影響がありますか?
A. 贈与の経緯や贈与された物の価値・性質、その贈与によって「特別の寄与」をした相続人自身が受けている利益等などを考慮し、その贈与が、実質的には当該相続人に対する贈与と同視できるようなときは、当該相続人が贈与を受けていた場合と同じように処理すべきであると考えられます。すなわち、実質的に寄与に対する清算がなされているとして寄与分を認めない、或いは寄与分額からそのような贈与等の額を差し引いた残額を寄与分とする、などの対応が必要となるでしょう。
Q.寄与分の額に何か制限がありますか?
A. 寄与分は、共同相続人間の具体的相続分という枠組みの中で、「被相続人の財産の維持又は増加」に「特別の寄与」をした者の貢献を反映させるものなので、相続財産の価額の範囲内でしか認められません。
また、被相続人が遺贈を行った場合には、寄与分の価格は、相続財産の価格から遺贈の価額を控除した額を超えることができません(民法904条の2第3項)。これは、寄与分よりも、被相続人の意思が尊重されることの表れであると考えられます。その為、相続財産の全てが他に遺贈された場合は、寄与分を定めることはできません。
Q.寄与分を定めた結果、他の相続人の遺留分(民法1042条)を侵害することになってしまいました。このような寄与分の定め方も可能なのでしょうか?
A. 民法上、寄与分と遺留分の関係は明示的に規定されておらず、遺留分を侵害するような寄与分を定めることもできると考えられます。そして、仮に相続財産の全てが遺留分とされるなどして、他の共同相続人の遺留分が侵害されるようなことがあっても、遺留分算定の基礎となる財産の価格を計算するにあたり、寄与分は考慮されないので、遺留分侵害額請求権(民法1046条1項)により、侵害額相当の金銭を支払う債務を負うことにもなりません(民法1047条1項柱書参照)。
但し、寄与分の額を定めるにあたっては、他の共同相続人の遺留分を実質的に考慮するという見解が、実務(東京高決平成3・12・24判タ794-215)・学説ともにしばしば採用されます。
Q.寄与分を請求する権利があることについて、訴訟で確認してもらうことはできますか?
A. まず、寄与分は、共同相続人間の公平を図る観点などから、あくまで相続分を修正するための制度として設けられたものであり、寄与分に相当する金銭の請求権が認められるわけではありません。その為、「寄与分を請求する権利」を訴訟で確認することはできません。
但し、上述の通り、寄与分について共同相続人間での協議が調わない、又はそもそも協議を行うことができない場合、寄与分を主張する者は、家庭裁判所に寄与分を定めるよう請求することができます(民法904条の2第2項)。その為、寄与分が認められるか、認められるとしていくら認められるかという点につき、家庭裁判所の判断を仰ぐこと自体は、不可能ではないと言えます。もっとも、寄与分は遺産分割の前提問題としての性格を有することから、遺産分割手続と離れて、独立して寄与分についてのみの審判を求めることはできません(浦和家飯能出審昭和62・12・4家月40-6-60)。
Q.寄与分について他の手段により請求できませんか?
A. 雇用等の契約に基づく報酬支払請求(民法623条など)や事務管理(民法697条1項)(※16)に基づく費用償還請求(民法702条1項)、不当利得に基づく利得返還請求(民法703条、704条)などとして請求できる可能性はあります。
しかし、相続人が被相続人の事業を手伝ったり、介護を行ったりするに際して、わざわざ雇用契約を締結する(その合意をする)ということは考えにくく、そのような合意が認められない状況下で、契約の成立を擬制することは困難です。また、事務管理に基づく費用償還請求権には、一般的に報酬請求権は含まれませんし、被相続人が相続人から法律上の原因なく「特別の寄与」を受けたとも必ずしも言えない(相続人・被相続人間には、その範囲を超える部分は別として、少なくとも扶養義務(民法877条1項)等が認められる場合が多い)と思われます。
その為、寄与分を求めるにあたっては、共同相続人間の協議又は家庭裁判所の調停・審判によるのが基本であると考えられます。
※16 事務管理:法律上の義務なく他人のためにその事務を管理(処理)すること。
Q.寄与分を他に譲渡したり、他者の有する寄与分を代わりに主張したりすることはできますか?
A. 相続分として寄与分を譲渡することは可能と考えられますが、寄与分を独立に譲渡することはできません。また、相続人の寄与分を、他者が代わりに行使することはできないものと考えられます
上述の通り、寄与分は、共同相続人間の公平を図る観点などから、あくまで相続分を修正するための制度として設けられたものです。そして、民法上、相続人が自己の相続分を他者に譲渡することが認められています(民法905条1項参照)。加えて、上述の履行補助者構成のように、判例は必ずしも「特別の寄与」を行った者しか寄与分を主張できないとはしていないので、状況に応じて修正が図られるものと思われます。その為、寄与分は、必ずしも一身専属権(※17)であるとは言えず、相続分を譲渡するのに伴って、譲渡人たる本来の相続人が有していた寄与分も譲受人に移転するものと考えられています。
もっとも、寄与分は、共同相続人間の公平を図る観点などから、あくまで相続分を修正するための制度として設けられたものであるので、相続分から離れて、寄与分のみを独立して譲渡することはできないと解されています。
一方、上述の通り、寄与分は相続分を定める上での機能的な概念であって金銭請求権ではないので、他者が代わって行使することが認められている金銭債権のように、それ自体強制執行(※18)することができるものではありません民法423条3項参照)。その為、他者が、相続人の有する寄与分を代わりに行使することはできないものと考えられます。
※17 一身専属権:特定の権利主体(当該権利を有する者)にのみ、当該権利を行使することが認められている場合、その当該権利のことを「一身専属権」と言います。一身専属権を他者が代わって行使することも(民法423条1項但書前段)、当該権利を相続人が相続することも(民法896条但書)できません。
※18 強制執行:国家権力の行使として、執行機関が、私法(国民ないし市民相互の関係を規律するもので、民法や商法が典型)上の請求権の強制的な実現を図る手続のこと。
寄与分と具体的相続分
Q.寄与分がある場合、どのように具体的相続分が算定されるのでしょうか?
A.寄与分を有する共同相続人がいる場合、その具体的相続分は、以下のように算定されます(民法904条の2第1項)。
(ⅰ)相続開始時において被相続人が有した相続財産の価額から、寄与分額を控除します(民法904条の2第1項)。これが、具体的相続分を算定する基礎財産(みなし相続財産)となります。
(ⅱ)みなし相続財産に、相続分(法定相続分(※19)又は指定相続分(※20))を乗じて、一応の相続分額を算定します。そして、寄与分のない相続人については、ここで算出された価格が、具体的相続分の価格に相当します。
(ⅲ)寄与分のある相続人については、(ⅱ)で算出された一応の相続分額に寄与分額を加算したものが具体的相続分額となります。
事例3
夫Aが死亡し、妻B、息子C及びDが共同相続人となりました。Aには1億円の金融財産があり、Dに2000万円の寄与分が認められることとなりました。
(ⅰ) みなし相続財産の算出
まず、相続開始時にAが有していた財産1億円からDの寄与分額2000万円を控除し、8000万円をみなし相続財産として、これを基準に共同相続人B・C・Dの具体的相続分を計算します。
(ⅱ) 一応の相続分の算出
B・C・Dの法定相続分は、それぞれ2分の1(民法900条1号)、4分の1(民法900条1号、900条4号本文)、4分の1となります。
よって、B・C・Dの一応の相続分(B・Cについては具体的相続分でもある)は、以下のように算出されます。
B:8000万円(みなし相続財産)×1/2(法定相続分)=4000万円(一応の相続分)
C:8000万円(みなし相続財産)×1/4(法定相続分)=2000万円(一応の相続分)
D:8000万円(みなし相続財産)×1/4(法定相続分)=2000万円(一応の相続分)
(ⅲ) 具体的相続分の算出(寄与分のある相続人のみ)
(ⅱ)で求めたDの本来の相続分に、Dの寄与分額2000万円を加算して、Dの具体的相続分を算出すると、以下の通りになります。
D:2000万円(一応の相続分)+2000万円(寄与分)=4000万円(具体的相続分)
※19 法定相続分:民法で定められた相続分のこと(民法900条各号)。
※20 指定相続分:被相続人が遺言によって指定した相続分のこと(民法902条1項)。
Q.共同相続人の中に、寄与分を有する者と、特別受益がある者とがいます。このような場合、各相続人の具体的相続分はそのように算定されるのでしょうか?
A. かかる場合、上のQと以下の点で異なります。
(ⅰ)被相続人の相続財産から、寄与分の価格は控除(民法904条の2第1項)し、特別受益の価格は加算(民法903条1項)します。
(ⅱ)上のQと相違点はありません(特別受益及び寄与分がない相続人の具体的相続分は、ここで算出された価格に相当します)。
(ⅲ)寄与分のある相続人は、(ⅱ)で算出された一応の相続分に寄与分額を加算したものが、特別受益のある相続人は、(ⅱ)で算出された一応の相続分から受益額を控除したものが、それぞれの具体的相続分となります。
事例4
夫Aが死亡し、妻B、息子C及びDが共同相続人となった。Aには1億円の金融財産があり、Dに2000万円の寄与分が認められることとなった。また、CはAから2000万円の特別受益を受けていた。
(ⅰ) みなし相続財産の算出
まず、相続開始時にAが有していた財産1億円に、Cが受けた特別受益2000万円を加算し、ここからDの寄与分額2000万円を控除して得た1億円をみなし相続財産として、これを基準に共同相続人B・C・Dの具体的相続分を計算します。
(ⅱ) 本来の相続分の算出
B・C・Dの法定相続分は、それぞれ2分の1(民法900条1号)、4分の1(民法900条1号、4号本文)、4分の1となります。
よって、B・C・Dの一応の相続分(Bについては具体的相続分でもある)は以下のように算定されます。
B:1億円(みなし相続財産)×1/2(法定相続分)=5000万円
C:1億円(みなし相続財産)×1/4(法定相続分)=2500万円
D:1億円(みなし相続財産)×1/4(法定相続分)=2500万円
(ⅲ) 具体的相続分の算出(寄与分又は特別受益のある相続人のみ)
(ⅱ)で求めたC・Dの一応の相続分を基に、Cについては特別受益2000万円を控除し、Dについては寄与分2000万円を加算して、それぞれの具体的相続分を算出すると、以下の通りになります。
C:2500万円(一応の相続分)−2000万円(特別受益)=500万円(具体的相続分)
D:2500万円(一応のの相続分)+2000万円(寄与分)=4500万円(具体的相続分)
特別寄与制度
Q.民法改正により導入された特別寄与制度(民法1050条1項)とはどういうものでしょうか?
A. 相続人でない者は、仮に「被相続人の財産の維持又は増加」(民法904条の2第1項)に貢献したとしても、「共同相続人」に含まれないので、寄与分を主張することはできません。これでは、寄与をした相続人でない者に酷な結果となってしまいます。
そこで、民法1050条1項は、「被相続人の親族」であって、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」者を「特別寄与者」とし、相続開始後(被相続人の死亡後:民法882条)、相続人に対して、寄与に応じた額の金銭である「特別寄与料」を請求することができると規定しました。
但し、相続人以外の被相続人の親族であっても、相続を放棄した者(民法939条)(※21)や、相続欠格(民法891条各号)又は推定相続人の廃除(民法892条、893条)により相続資格を喪失した者は、「特別寄与者」となり得ません(1050条1項括弧書き)。
なお、相続人が複数存在する場合、各相続人は、特別寄与料に法定相続分(民法900条、901条)若しくは指定相続分(民法902条)を乗じた額を負担することになります(民法1050条5項)。例えば、特別寄与料が1000万円で、2人の相続人(子「X」と子「Y」とする)が存在し、相続分の指定がない場合、XとYは、法定相続分(それぞれ2分の1(民法900条4号本文))に従って、各々1000万円×1/2=500万円を負担することになります。
※21 相続放棄:相続開始後になされる、相続人が相続の効果が自己に及ぶことを拒否する旨の意思表示のこと。相続を放棄しようとする者は、その旨の家庭裁判所に申述しなければならず(民法938条)、これにより初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。
Q.被相続人から寄与に対する対価の支払いを受けている場合でも、特別寄与料の請求はできますか?
A.できません。民法1050条1項が規定する特別寄与制度は、親族による被相続人に対する貢献が「無償で」行われた場合に、その貢献に報いるための制度です。その為、既に被相続人から貢献への対価を受け取っていた場合や、契約や遺言で貢献に報いるため財産を譲る(民法549条、554条、964条)、などとされていた場合は、特別寄与料の請求はできません。
Q.特別寄与料の請求と相続とは、どのような関係にあるのでしょうか?
A. 相続人の寄与分が遺産分割手続(民法907条1項、2項本文)の中で定められ、また具体的相続分の算定の際に考慮されるものであるのに対し、特別寄与料の請求は相続とは全く別の制度です。従って、特別寄与料は遺産分割手続の中で考慮されることはありません。また、遺産分割手続後に、特別寄与料の請求がなされたとしても、そのことのみで遺産分割の効力に影響が及ぶことはありません。
Q.被相続人が遺言で「特別の寄与があったとは認めない」或いは「特別寄与料は○○円とする」などとしていた場合、どのように扱うべきなのでしょうか?
A. 被相続人が遺言で寄与分について定めていた場合と同様に、特別寄与料の場合も、その部分に限って無効なものとして扱われます。その為、上述のような遺言の存在によって特別寄与料の請求が妨げられたり、遺言に定められた特別寄与料の価格に拘束されたりすることはありません。
Q.特別寄与料の請求権があることについて、訴訟で確認してもらうことはできますか?
A. 特別寄与料に関する当事者間の協議(民法1050条2項本文参照)、家庭裁判所による調停又は審判(民法1050条2項本文)が行われる前の段階では、請求権が存在するかを訴訟で確認してもらうことはできません。というのも、特別寄与料の請求権は、特別寄与者が請求し、協議、調停又は審判が行われることによって初めて形成される権利であって、それ以前の段階では、まだ具体的な権利となっていないためです。また、同じ理由で、相続人の側から、特別寄与者に対して特別寄与料を支払う義務がないことの確認請求をすることもできません。
Q.被相続人の親族とは、具体的にどのような者を指すのでしょうか?
A. 親族とは、①6親等内の血族(民法725条1号)、②配偶者(民法725条2号)、③3親等内の姻族(民法725条3号)を指します。この内、②配偶者は常に相続人となる(民法890条前段)ので、特別寄与者になり得る親族とは、①か③のいずれかに該当し、かつ相続人ではない者ということになります。
例えば、夫A、妻B、長男C、Cの妻D、孫(CD間の子)Eがいたとします。Aが亡くなると、BとCが相続人となります(Bにつき民法890条前段、Cにつき民法887条1項)。一方で、DやEがAの介護を無償で引き受け、その結果、Aの財産の維持・増加に貢献したといえる場合、「特別寄与者」として、「特別寄与料」の請求権が認められる可能性があります。
Q.特別寄与者として認められる寄与とは、どの程度のものを指すのでしょうか?
A. 相続人の寄与分と同じ「特別の寄与」(民法904条の2第1項、1050条1項)という表現が使われていますが、その意味は異なると考えられています。
寄与分の場合、「特別の寄与」とは「通常期待される程度を超える」ものであることが要求されていますが、特別寄与者の場合は「貢献の程度が一定程度を超える」ことでよいと考えられています。
一方で、寄与分の場合は、被相続人に対し「事業に関する労務の提供」や「財産上の給付」、「療養看護」、「その他の方法」で、かつ有償であっても寄与分が認められる余地はある(特別受益の控除につき、前述のQ参照)のに対して、特別寄与の場合は、「療養看護」「その他の労務の提供」で、かつ無償のもののみが対象となります。
Q.「特別寄与料」の額は、どのように決めるのでしょうか?
A. 「特別寄与料」の請求を認めるかどうか、認めるとして「特別寄与料」の額はいくらとなるかについては、まずは特別寄与者と相続人との間(当事者間)の協議で決めることとなります(民法1050条2項本文参照)。そして、かかる協議が調わない、又は協議をすることができない場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対し、調停や審判などの「協議に代わる処分」を求めることができます(民法1050条2項本文)。
また、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません(民法1050条4項)。それ故、相続人が特別寄与料の負担を負うことになるのは、相続財産の範囲に限定されることになります。
Q.家庭裁判所の審判を待っていたのでは不安です。「特別寄与料」の仮差押(※22)、仮処分(※23)の申立てを行うことはできるのでしょうか?
A. 特別の寄与に関する処分についての審判又は調停の申立てがあり、強制執行を準備し又は申立人の急迫の危険を防止する必要があるときは、申立てを行い、それが家庭裁判所(又は高等裁判所)に認められれば、特別の寄与に関する処分の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の保全処分が命じられます(家事事件手続法216条の5)。
※22 仮差押:金銭債権について、裁判所の判決等が出されるまでの間に、強制執行が不可能ないし著しく困難になるおそれがある場合、債務者に対して目的物の処分を禁止し、引き当てとなる財産を保全することができます。
※23 仮処分:金銭債権以外の特定物に関する請求権について、裁判所の判決等が出されるまでの間に、強制執行が不可能ないし著しく困難になるおそれがある場合、債務者に対して現状の変更を禁止することができます。
Q.「特別寄与料」の請求について、期間制限はありますか?
A. 「特別寄与者」が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき(消滅時効期間)、又は相続開始の時から1年を経過したとき(除斥期間(※24))は、家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」(民法1050条2項本文)を求めることはできなくなります(民法1050条2項但書)。
※24 除斥期間:一定の期間内に権利を行使しないと、その期間の経過によって権利が当然に消滅するような期間のこと。「時効により消滅する」と条文上規定されていても、それが消滅時効であれば、時効期間が経過しても当然には権利の喪失の効果は生じず、当事者の援用(民法145条:時効の利益を受けようとする意思表示)を待って初めて当該効果が発生します。一方で、それが除斥期間であれば、当事者による援用を待たずして、期間の経過とともに当然に権利が消滅してしまいます。
Q.内縁配偶者やパートナーシップ制度によるパートナーなどは、「特別寄与者」になりえますか。
A. 内縁配偶者やパートナーシップ制度によるパートナーは、親族たる「六親等内の血族」(民法725条1号)・「配偶者」(民法725条2号)・「三親等内の姻族」(民法725条3号)のいずれにも該当せず、「被相続人の親族」(民法1050条1項)に当たらないので、「特別寄与者」になり得ません。
そこで、内縁配偶者やパートナーシップ制度によるパートナーの方による貢献に報いる方法としては、
①”被相続人との委任契約に基づく費用償還請求権(民法650条1項)ないしは雇用契約に基づく報酬支払請求権(民法623条)等を行使する
②”被相続人又は相続人に対する事務管理を理由とする費用償還請求権を行使する(民法702条1項)
③”被相続人に対する不当利得返還請求権を行使する(民法703条、704条)
方法等が考えられます。しかし、上述の通り、①”〜③”の請求は認めるのは困難であり、現実的な救済とは言えません。そのため、被相続人に、寄与の対価を贈与又は遺贈してもらうのが、内縁配偶者やパートナーシップ制度によるパートナーにとって最も現実的な救済手段となるかもしれません。