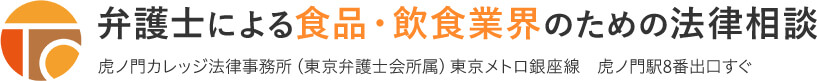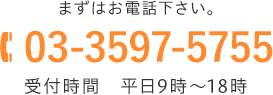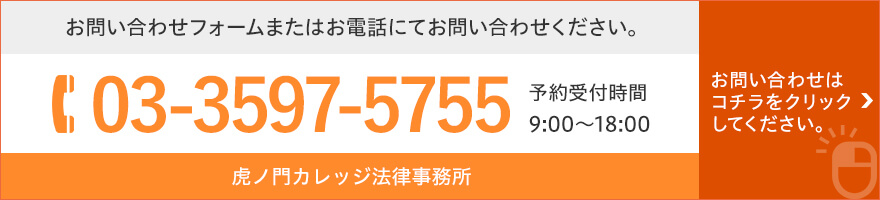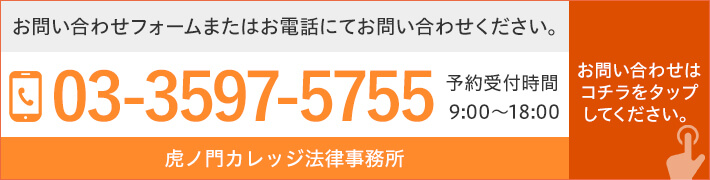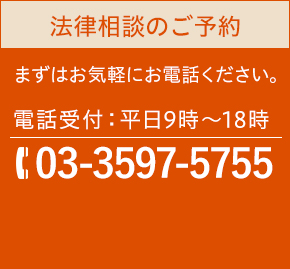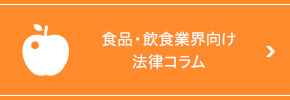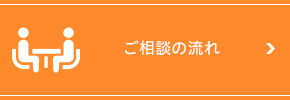食品の表示・広告に関する法律

食品の表示・広告に関する主な法規制としては、以下の法律が挙げられます。
Contents
食品表示法
(1)概要
食品表示法は、食品表示に関する基準を定める法律で、食品衛生法・JAS法・健康増進法の三法の食品表示に関する規定を一元化した法律として制定され、平成27年4月に施行されました。
食品関連事業者等は、販売(不特定又は多数の者に対する譲渡を含む)する食品について、食品表示法に基づき策定された新しい「食品表示基準」に従った表示をすることが義務付けられています(1条・5条)。
食品表示法は、主な内容として、食品表示施策の目的(1条)や基本理念(3条)をはじめ、食品表示基準の策定手続(4条)及び同基準の遵守(5条)、同法に違反する表示に対する措置(6条以下)などを規定しています。
食品表示法は、食品表示施策の基本理念(3条)として、まず、消費者の安全確保や消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保、消費者に対する必要な情報の提供といった消費者の権利の尊重と、消費者の自立の支援を基本として講ぜられなければならないと規定されました(1項)。それとともに、小規模な食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響や食品関連事業者間の公正な競争の確保など、食品関連事業者側の事情についても配慮することとされています(2項)。
(2)食品表示基準
「食品表示基準」(内閣府令)は、食品表示法の委任を受けて、食品の安全確保及び消費者の選択の機会の確保のため、食品に関する表示事項や遵守事項の基準を定めたものです。食品関連事業者等が食品を販売する場合を適用の対象としており、レストラン等の「加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合」には、生食用牛肉の注意喚起表示に関する食品表示基準40条を除き、適用されません。
食品表示基準では、食品を「加工食品」「生鮮食品」「添加物」に区分し、それぞれの表示についてのルールを規定しています(加工食品は第2章、生鮮食品は第3章、添加物は第4章)。そして、加工食品と生鮮食品には、消費者向けに販売する「一般用」と、加工食品の原材料となるなど消費者向けに販売される形態となっているもの以外の「業務用」の区分があります。食品表示基準は、これらの区分ごとに、「義務表示事項」、「任意表示事項」、「表示方式」、「表示禁止事項」の4つを定めており、食品表示はかかる基準に従って行う必要があります。
なお、食品表示基準では、食品関連事業者以外の販売者(反復継続性のない販売を行う者)については、食品関連事業者とは別に、表示事項等が定められています(加工食品・生鮮食品・添加物の各章の第2節)。食品関連事業者に比べて、義務表示事項が少なく規定されています。
ア 義務表示事項
食品表示基準が義務付ける表示事項には、「横断的義務表示事項」「個別的義務表示事項」があります。「横断的義務表示事項」には、全ての食品に共通して義務付けされるものと、一定の範囲の食品に共通して義務付けられるものがあります。例えば、一般用加工食品の「横断的義務表示事項」として、前者(全ての一般加工食品に共通)については、名称や消費期限又は賞味期限、内容量(又は固定量及び内容総量)、食品関連事業者の名称と住所等(基準3条1項)が、後者(一定の範囲の一般加工食品に共通)については、特定原材料を原材料とする加工品等についてのアレルゲン、輸入品についての原産国名や、平成29年9月の食品表示基準の改正により義務付けられることになった輸入品以外の加工食品に対する原料原産地などがあります(基準3条2項)。一般用加工食品の「個別的義務表示事項」は、個別の食品ごとに、食品表示基準別表第19に定められています(基準4条)。
なお、義務表示事項については、一定の場合に義務表示の一部を省略できる旨の規定があります(一般用加工食品については、食品表示基準3条3項・4条ただし書き)。また、義務表示の特例として、表示を要しない場合の規定もあります(一般用加工食品については、食品表示基準5条)。
イ 任意表示事項
任意表示事項は、表示することが義務づけられてはいないものの、当該事項を表示するにあたっては特定の表示方法に従う必要がある表示です。例えば、一般用加工食品に使用した原材料が有機農産物であるなど、特色のあるものである旨を表示する場合には、当該原材料の製品の原材料及び添加物に占める重量の割合等を表示しなければなりません(基準7条の表)。
任意表示事項の中には、一般用加工食品についての食物繊維の量など(基準6条)、食品関連事業者が表示することを積極的に推奨されている「推奨表示事項」もあります。
ウ 表示方式
食品表示基準が定めている表示すべき内容は、表示方式に従って表示する必要があります。例えば、一般用加工食品については、容器包装の見やすい箇所に、表示事項を一括して、規定の大きさ以上の文字で表示することなどを規定しています(基準8条)。
エ 表示禁止事項
食品表示基準は、義務表示事項や任意表示事項について、消費者に誤解を与えるような表示をすることを禁止しています。例えば、一般用加工食品についての9条1項や一般用生鮮食品についての23条1項は、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認される用語を表示することや、機能性表示食品に疾病の治療・予防効果を標榜する用語を表示することなどを禁止しています。
(3)違反に対する措置
消費者庁長官等は、表示の適正を確保するため必要がある場合には、食品関連事業者等に対し、事業所等への立入検査・報告要求等や、食品・原材料の無償収去ができ(法(以下、本項内において同じ)8条・9条)、これらを妨げた場合には罰則があります(21条1号・同2号・22条)。
食品関連事業者が、表示すべき事項を表示していない食品を販売し、又は遵守すべき事項を遵守していない場合、消費者庁長官等は、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守するよう指示・命令することができます(6条1項・同3項・同5項)。また、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項に関する食品表示基準違反の行為について緊急の必要があると認められるときは食品の回収命令等を行うこともできます(6条8項)。これらの指示又は命令は公表されます(7条)。これらの命令に従わない場合には罰則があります(17条・20条・22条)。ただし、内閣府令が定める食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項についての表示基準の違反や、原産地・原料原産地表示について虚偽の表示をした場合には、指示・命令を介さず(直罰)、懲役(令和4年の刑法改正(未施行)により拘禁刑。以下、同じ)又は罰金が科される可能性があります(18条・19条・22条)。
なお、平成30年の食品表示法の改正により、内閣府令が定める食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項についての表示基準に違反した食品を、食品関連事業者が自主回収する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく届出をすることが義務付けられました(10条の2)。この義務に違反した場合にも罰則があります(21条・22条)。
その他、食品表示違反に対しては、民間の消費者団体による差止請求(11条)がなされる場合もあります。
食品衛生法
(1)概要
食品衛生法は、食品の安全確保を目的とした法律であり、医薬品・医薬部外品等を除いたすべての飲食物を対象としています。内容としては、食品の表示・広告に関する規定のほか、有害食品の販売の禁止、食品や添加物、食品等に直接触れる器具や容器包装についての規格基準の策定、検査、営業許可制度等について規定しています。なお、食品衛生法については、平成30年に、HACCPに沿った衛生管理の制度化や営業届出制度の創設などを内容とする大きな改正が行われました。
食品衛生法は、食品表示法に一元化された三法のうちの一つですが、食品表示法に移行しなかった表示に関する規定については、従前どおり食品表示を規制する規定として機能しているため、注意が必要です。
(2)食品の表示・広告に関する規定
食品衛生法は、食品や添加物、器具、容器包装に関し、公衆衛生に危害を及ぼすおそれのある虚偽・誇大な表示・広告を禁止しています(20条)。対象となる表示・広告は、「公衆衛生に危害を及ぼすおそれのある」ものに限られます。例えば、「アレルギーを起こさない小麦を使用しています」と表示することは、食物アレルギーを有する消費者が口にしてしまうと重大な健康被害を引き起こすおそれがあるため、本条に違反するでしょう。これに対して、原産地を偽るような表示に関しては、健康被害は生じないため、同条の規制対象とはなりません。
(3)違反に対する措置
消費者庁長官等は、必要があると認めるときは、営業者等に対し、営業場所等への立入検査・報告要求等や、食品等の無償収去をすることができ(28条)、これらを妨げた場合には罰則があります(85条1号・同2号・88条)。また消費者庁長官等は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法や同法に基づく処分に違反した者の名称等を公表することができます(69条)。
そして、上記(2)のような虚偽・誇大表示等に対し、消費者庁長官等は、営業者等に対し、その食品等の廃棄や食品衛生上の危害を除去するために必要な処置の命ずることができます(59条2項)。また、前述した平成30年の食品衛生法の大改正により、食品等の自主回収報告制度が創設され(58条)、虚偽・誇大表示等の禁止の規定に違反し又は違反するおそれのある食品等の自主回収もこの制度の対象となっています。したがって、営業者が、このような食品等を自主回収する場合には、例外(58条1項柱書括弧書き)に該当しない限り、遅滞なく、都道府県知事等に届出をしなければならず、これを行わず、又は虚偽の届出をした場合には、罰金が科される可能性があります(85条3号・88条)。
また、食品衛生法の虚偽・誇大表示等の禁止に違反した場合、営業許可の取消し・営業禁止・営業停止といった処分の対象となる(60条1項)ほか、懲役又は罰金が科される可能性があります(82条・88条)。
JAS法(農林物資の規格化等に関する法律)
(1)概要
JAS法は、農林水産分野において適正かつ合理的な規格を制定し、認証や試験等の実施を確保するとともに、農林物資の品質表示(ここでの農林物資は飲料食品以外)の適正化を講じることによって、農林物資の品質の改善や取扱いの合理化・高度化、取引の円滑化、消費者の合理的な選択の機会の拡大を図り、農林水産業等の健全な発展と消費者の利益の保護に資することを目的とした法律です。
JAS法は、JAS規格制度や品質表示基準制度について規定しています。
JAS法の対象となる農林物資の中の飲食料品からは、医薬品、医薬部外品等が除かれます。これまで、酒類も対象から除かれていましたが、改正により、令和4年10月1日から有機加工食品のJAS規格の対象に有機酒類が追加されました。
(2)表示に関する規定
ア JAS規格制度
JAS規格制度は、農林水産大臣が制定する日本農林規格の格付検査に合格した製品にJASマークの貼付を認め、その規格を満たすことを保証する制度です。従来、JAS規格は、農林物資の品質等を対象としていましたが、平成29年6月の改正により、農林物資の生産方法や取扱方法、試験方法等にも拡大されました。
JASマークの表示は任意ですが、JAS規格に適合しない製品にJASマークを貼付したり、格付検査に合格していない製品にJASマークと誤認されるようなまぎらわしい表示を付したりすると、JAS法に違反することとなります(37条・38条)。
イ 品質表示基準制度
旧JAS法では、飲食料品の品質に関する表示基準について定めていましたが、食品表示法の制定に伴い、これらは廃止されました。
(3)違反に対する措置
JAS規格制度においては、格付検査に合格した後も認証を受けた製品が引き続き基準に適合しているか、JASマークの表示業務が適正に行われているかなどについて、定期的又は必要に応じて登録認証機関による調査が行われ、その結果に応じて改善請求や認証の取消しなどの措置がとられることがあります。農林水産大臣等が、認定事業者やJAS規格に関する不適切な表示を行った者等に対し、立入検査や報告要求等を行うこともでき(65条・66条)、これを妨げた場合には罰則があります(81条2号・83条)。
農林水産大臣等は、認定事業者の格付や格付の表示が適当でない場合には、改善や表示の除去・抹消を命ずることができ、正当な理由がなくこれらの命令に応じなかったときは、その旨を公表することができます(39条)。除去・抹消命令に違反した場合には罰則があります(78条7号・83条)。さらに、農林物資の取扱業者は、格付の表示が付してある所有農林物資について、規格に適合しないことが確実となる事由として主務省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく表示を除去・抹消しなければなりませんが(41条・41条の2)、これに違反した場合等にも罰則があります(78条9号・同10号・83条)。
また、農林水産大臣等は、事実に反してJAS規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合には、当該表示を行った者に対し、必要な措置をとるよう指示をすることができ、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができます(68条)。
そして、認証を受けていない製品にJASマークやこれと紛らわしい表示をして販売する行為については、懲役又は罰金が科される可能性があります(78条5号・同6号・83条)。有機農産物の認証を受けていない農産物に「有機○○」等と表示をして販売したような場合には、表示の除去・抹消や販売禁止の命令を受ける可能性があり(64条)、これらの命令に違反したときにも罰則があります(78条14号・83条)。
健康増進法
(1)概要
健康増進法は、国民の健康の増進、国民保健の向上を目的とする法律です。内容としては、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針(7条)や、地方公共団体の健康増進計画の策定、国民健康・栄養調査の実施、保健指導等の実施、特定給食施設の届出や同施設における栄養管理等、受動喫煙を防止するための規制・措置などと、特別用途表示等の食品の表示について規定しています。
健康増進法には、食品の栄養表示に関する基準についての規定がありましたが、食品表示法の制定に伴い廃止されました。
(2)食品表示に関する規定
ア 特別用途表示(43条以下)
「特別用途表示」とは、販売する販売に供する食品について、乳児用・幼児用・妊産婦用・病者用等の内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示のことです。乳児の発育や病者の健康回復などの特別の用途に適しているという表示を行って食品を販売するためには、消費者庁長官の許可を受ける必要があります。健康増進法の委任を受けた内閣府令では、それぞれの用途に応じて表示しなければならない事項を定めています。
イ 虚偽・誇大表示の禁止(65条1項)
健康増進法は、健康保持増進効果等の内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示及び著しく人を誤認させるような表示を禁止しています。規制対象について「何人も」と定めているため、食品の販売業者や製造業者等だけでなく、広告に携わる広告代理店や雑誌・新聞社等もこれに含まれることとなります。
「健康増進効果等」については、消費者庁により公表されている「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(最終改定:令和4年12 月5日)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms214_221205_01.pdf)というガイドラインにおいて、具体的に示されています。例えば、同ガイドラインでは、虚偽誇大表示に該当する例として、十分な実験結果等の根拠が存在しないにもかかわらず、「3か月間で○キログラムやせることが実証されています。」と表示する場合等を挙げています。
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
第3 景品表示法及び健康増進法について
4 禁止される表示
⑵ 健康増進法上の虚偽誇大表示
ア 事実に相違する表示
「事実に相違する」とは、広告等に表示されている健康保持増進効果等と実際の健康保持増進効果等が異なることを指す。このため、例えば、十分な実験結果等の根拠が存在しないにもかかわらず、「3か月間で○キログラムやせることが実証されています。」と表示する場合や、体験談そのものや体験者、推薦者が存在しないにもかかわらず、体験談をねつ造した場合、ねつ造された資料を表示した場合等は、これに該当することとなる。
(3)違反に対する措置
ア 特別用途表示の規制の違反の場合
許可を受けずに特別用途表示を行って食品を販売した場合には、罰則があります(72条2号・75条)。
また、消費者庁長官等は、必要があると認めるときは、特別用途食品の製造施設等への立入検査や試験のために特別用途食品を収去することができ(61条)、これらを拒否した場合には罰則があります(74条2号・75条)。消費者庁長は、特定用途表示の許可に係る食品について、内閣府令で定める事項の表示をしなかったときや虚偽の表示をしたとき、許可後に特別用途表示をすることが適切でないことが判明したときは、許可を取り消すことができます(62条)。
イ 虚偽・誇大表示広告の禁止違反の場合
虚偽・誇大表示広告の規制の違反行為を行った場合には、消費者庁長官等による指導・勧告、勧告に係る措置をとるべきことの命令がなされ(66条)、その命令に従わない場合には、罰則があります(71条)。
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
(1)概要
独占禁止法は、事業者間の公正かつ自由な競争を促進することで、消費者の利益を確保することを目的とした法律です。市場における自由な競争に対して悪影響を及ぼすような行為が規制されています。
(2)表示に関する規定
独占禁止法上の表示に関する規制として、ぎまん的顧客誘引(独占禁止法19条、2条9項6号ハ、一般指定8項)があります。これは、商品・役務の内容や取引条件等を実際のもの又は競争者のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を不当に誘引する行為をいいます。後述する景品表示法上の不当表示に該当するような行為がこれにあたりますが、ぎまん的顧客誘引は、景品表示法の表示規制と異なり、事業者に対する表示も規制対象になります。
(3)違反に対する措置
公正取引委員会は、独占禁止法違反の疑いがある場合には、関係者に出頭を命じて事情聴取したり、帳簿書類等の提出を命じたり、営業所その他必要な場所へ立ち入り、業務や財産の状況を検査するなどの調査を行うことができます(47条)。これらを妨げた場合には罰則があります(94条・95条)。公正取引委員会は、独占禁止法の適正な運用を図るため、事業者の秘密を除き、必要な事項を一般に公表することができます(43条)。
調査の結果、ぎまん的顧客誘引等の不公正な取引方法に該当する行為があると認められる場合、公正取引委員会により当該行為の差止め、契約条項の削除その他必要な措置(排除措置命令)が命ぜられる可能性があります(20条1項)。確定した排除措置命令に従わない場合には罰則があります(90条3号・95条)
また、競争事業者により差止請求(24条)や損害賠償請求(25条)がなされる可能性もあります。
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
(1)概要
景品表示法は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、消費者による自主的・合理的な選択を阻害するおそれのある行為を制限・禁止することにより、消費者の利益を保護することを目的とする法律であり、独禁法上のぎまん的顧客誘引や不当な利益による顧客誘引を規制するための特別法にあたります。内容としては、不当景品類の制限・禁止の制度と、不当表示の禁止の制度等が規定されています。特定の事項の表示を義務づける食品表示法とは反対に、景品表示法は特定の表示を禁止しています。
(2)表示に関する規定
景品表示法が禁止している不当表示は、優良誤認表示、有利誤認表示、その他の不当表示の3つに大別されます。
ア 優良誤認表示(5条1号)
商品やサービスの品質について、実際のものよりも著しく優良であると示して、消費者の商品選択に影響を与えるような表示です。食品表示の例を挙げると、国産の牛肉であると表示していたが、実際には外国産の牛肉である場合、当該表示は優良誤認表示となります。実例として、兵庫県のある事業者が、広告媒体に「但馬牛」を提供しているように表示をしながら他県産和牛を提供していたことが、優良誤認表示に該当するとして、後述する措置命令を受けた事案があります。
イ 有利誤認表示(5条2号)
商品やサービスの取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると示して、消費者の商品選択に影響を与えるような表示です。例えば、通常販売価格の半額と表示していたが、そもそも通常販売価格が設定されていなかった場合、当該表示は有利誤認表示となります。
ウ その他の不当表示(5条3号)
内閣総理大臣により指定された不当表示で、2022年12月現在、以下の6つがあります。
①無果汁の清涼飲料水等についての表示(無果汁告示)
②商品の原産国に関する不当な表示(原産国告示)
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示(融資費用告示)
④不動産のおとり広告に関する表示(不動産おとり広告告示)
⑤おとり広告に関する表示(おとり広告告示)
⑥有料老人ホームに関する不当な表示(有料老人ホーム告示)
(3)違反に対する措置
ア 調査
消費者庁長官等は、後述する措置命令や課徴金納付命令等を行うために必要がある場合には、事業者等に対し、事務所等への立入検査や報告要求等ができ(29条)、これらを妨げた場合には罰則があります(37条・38条)。
イ 措置命令
食品表示が景品表示法の不当表示に当たる場合は、消費者庁長官等は、事業者に対し、その行為の差止め、再発防止策の実施などを命ずる措置命令を行うことができます(7条1項)。この命令に従わない場合には罰則があります(36条・38条~40条)。違反の事実が認められない場合であっても、そのおそれのある行為がみられた場合は、指導の措置が採られることがあります。
消費者庁や公正取引委員会のホームページでは、毎月のように、措置命令を行った事例が公表されており、令和3年度は、国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による措置命令が41件、指導が172件となっています。
措置命令の発令に関連して、景品表示法は、不実証広告規制を規定しています(7条2項)。これは、不当表示事件の中で最も件数が多い「優良誤認表示」を効果的に規制するためのものです。消費者庁長官は、優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が合理的な根拠を示す資料を提出しない場合には、その表示は、優良誤認表示とみなされます。令和3年度の措置命令41件中、優良誤認表示によるものが30件で、そのうち7割(21件)が不実証広告規制によるものとなっています。
ウ 課徴金納付命令
優良誤認表示と有利誤認表示に該当する行為に対しては、課徴金納付命令が課される場合もあります(8条1項柱書)。措置命令は、事業者が自ら不当表示であることを知らなかった場合にも課せられますが、課徴金納付命令は、事業者が、自ら行った表示が不当表示であることを知らず、知らないことにつき「相当の注意を怠った者でない」と認められるときは課せられません(8条1項ただし書)。令和3年度は、13名の事業者に対して、15件の課徴金納付命令が行われました。
上記の不実広告規制については、課徴金納付命令との関係では、優良誤認表示と「推定される」ので、事業者は、優良誤認表示ではないことを証明することにより、課徴金納付命令を争うことができます(8条3項)。
なお、平成26年6月の改正により、事業者に対し、その規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容等に応じ、表示等管理措置をとることが義務付けられました(26条1項)。この措置と、課徴金納付命令との要件との関係について、消費者庁がまとめた「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」というガイドライン(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160208premiums_3.pdf)によると、事業者が、必要かつ適切な範囲で、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成 26 年内閣府告示第 276 号)に沿うような具体的な措置を講じていた場合には、「相当の注意を怠った者でない」と認められると考えられています。
エ その他
その他、不当表示に対しては、適格消費者団体による差止請求(30条1項)や、公正競争規約という業界の自主的なルールによる規制(31条)などもあります。公正競争規約は、令和2年6月24日時点で102規約が設定されており、このうち、表示に関係するものは65規約(食品関係35規約)となっています。公正競争規約を運用する団体は、社団法人全国公正取引協議会連合会のホームページでご確認ください。
不正競争防止法
(1)概要
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争とこれに関する国際約束の的確な実施を確保することで、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。内容としては、他人の著名表示の使用や営業秘密の侵害等の不正競争を規定し、これらの行為により営業上の利益を侵害された事業者に民事救済手段を設けるほか、公益を害する行為に対しては刑事罰を定めています。国際約束に基づき、外国の国旗や国際機関の標章等の商業上の使用の禁止などについても定めています。
(2)表示に関する規定
不正競争防止法は、商品やその広告等に、原産地や品質・内容・製造方法・用途・数量について誤認させるような表示をすることや、そのような表示をした商品の譲渡・引渡しと、そのための展示・輸出・輸入等を「誤認惹起行為」として禁止しています(2条1項20号)。食品表示の例を挙げると、外国産の牛肉を、兵庫県の写真とステーキ等の神戸牛を彷彿とさせる表示をした包装箱に入れ、原産地を表示せずに販売した場合、誤認惹起行為となります。
(3)違反に対する措置
不正競争防止法に違反した場合には、営業上の利益を侵害された競業者から、民事上の差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)を受ける可能性があります。
また、不正の目的をもって上記誤認惹起行為を行った場合や商品の原産地等について虚偽の表示を行った場合には、懲役又は罰金が科される可能性があります(21条2項1号・同5号・22条)。
その他の法規制
上記のほか、食品表示に関する法律や、特定の取引分野における表示・広告を規制する法律としては、以下のような法律があります。
(1)計量法
計量法は、適正な計量の基準を策定する法律であり、食品の内容量は、同法に定められた記載方法に従って表示しなければなりません。
計量法は、法定計量単位(ℊ・㎏・㎖・ℓ等)により取引をする者に、正確に計量をするよう努めることを義務づけています(10条1項)。特に、計量単位により取引されることの多い消費生活関連物資であって、量目公差(政令で定める誤差の基準)を課すことが適当であるとして、政令が定める「特定商品」(食肉、野菜、魚介類など29種類)に該当する食品を計量販売する場合には、定められた単位で記載することや、内容量の誤差を定められた基準から不足しないようにすることが必要となります(12条。密封をした特定商品についての内容量等の表記について13条、輸入した特定商品の内容量等の表記について14条)。
これらの規定に違反している場合、都道府県知事等は、販売事業者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告し、勧告に従わなかったときはその旨を公表することができます(10条2項・同3項・15条1項・同2項)。12条・13条の規制に関する勧告ついて、正当な理由なく勧告に係る措置が取られなかったときは、都道府県知事等は、その勧告に係る措置を命ずることができます(15条3項)。その命令に違反した場合には罰則があります(173条2号・177条)。
(2) 資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)
資源有効利用促進法は、資源の回収・利用を目的として、容器包装の識別表示等について定める法律です。食品の紙製容器包装やプラスチック製容器包装、スチール製・アルミニウム製の缶やペットボトル等の「指定表示製品」については、分別回収を容易にするために、それぞれ表示すべき事項(指定表示製品の材質)や指定表示製品の製造事業者及び販売事業者等(指定表示事業者)が守るべき事項(マークの様式や表示方法等)が定められています(24条)。
一定規模以上の指定表示事業者が適切な表示をしない場合には、勧告・公表・命令等の行政措置(25条)を受ける可能性があります。命令に従わない場合には罰則があります(42条・44条)。
(3)酒類業組合法(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律)
酒類業組合法は、酒税の確保及び酒類の取引の安定を図ることを目的とする法律で、酒類販売における表示義務についても規定しています。酒類の容器又は包装には、酒税の検査・取締の見地から、酒類の品目やアルコール分、製造場の所在地等の項目を、定められた記載方法に従って表示するよう義務付けられており(86条の5、施行令8条の3)、この義務に違反する場合には罰則があります(98条1号の2・100条)。
また、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため、財務大臣は、酒類の製法、品質その他の事項の表示について基準を定めることができ(86の6、施行令8の4)、この規定に基づき、清酒の製法品質表示基準、果実酒等の製法品質表示基準、酒類の地理的表示に関する表示基準、二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準が定められています。酒類における有機の表示基準は、JAS法の改正に伴い、令和4年10月1日に廃止されました(令和7年9月30日まで経過措置あり)。酒類業者がこれらの基準を遵守しない場合は、指示・公表の行政措置を受けるおそれがあります(86条の6第3項・同4項)。特に重要な基準に関する指示に従わない場合については、命令・罰則(86条の7・98条第2号・100条)の規定があります。
(4)牛トレーサビリティ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)
牛トレーサビリティ法は、牛の個体識別情報を管理することにより牛海綿状脳炎(BSE)のまん延防止措置の実施の基礎とするとともに、生産・流通・消費の各段階において個体識別情報の提供を促進するため、国内牛肉の個体識別番号の表示や帳簿の備付けを義務づける法律です。
牛肉の販売業者は、販売する精肉の個体識別番号を、容器包装や店舗の見やすい場所に表示しなければなりません(15条)。また、主として焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキを提供している「特定料理提供業者」は、これらの料理を提供する場合、料理や店舗の見やすい場所に個体識別番号を明瞭に表示する必要があります(16条)。
個体識別番号の表示が適切にされていない場合、勧告や命令等の行政措置(18条)を受ける場合があります。命令に従わない場合には罰則があります(23条3号・24条)。
(5)米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)
米トレーサビリティ法は、米穀等の取引等の情報の記録や産地情報の伝達を義務付けることにより、米穀等に関し、安全性を欠く米穀等の流通を防止し、適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の基礎とするとともに、消費者への米穀等の産地情報の提供を促進するための法律です。
米穀事業者は、米穀や米加工品などを販売する際に、米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を表示することが義務付けられています(8条)。
適切な表示が行われていない場合、勧告・命令等の行政措置を受ける場合があります(9条)。命令に従わない場合には罰則があります(12条4号・13条)。
(6)薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の品質や有効性・安全性を確保するために必要な規制を定める法律です。
薬機法は、承認を受けていない医薬品等医療機器、再生医療等製品の広告を禁止しています(68条)。例えば、健康食品等の販売において、医薬品として承認を受けてないにも関わらず、医薬品と同等の効能をうたった場合には、これに違反することになります。
薬機法の広告規制違反は、その行為の中止や再発防止等の措置命令の対象となります(72条の5)。罰則もあります(85条5号・90条)。また、薬機法に違反した医薬品等の製造・販売業者等は、業務停止や許可・登録取消しなどの行政処分を受けることもあります(75条、75条の2等)。
(7)GI法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)
食品の表示や広告についても、多くの知的財産権が関わってきます。表示の内容や表現が、他者の商標権や商号等の営業標識についての権利を保護する法律(商標法や会社法・商法等)や、キャッチコピー・写真・イラスト・デザイン等に関わる知的創造物についての権利を保護する法律(著作権法・意匠法等)に抵触しないよう注意しなければなりません。
さらに、平成26年に「GI法」が制定され、食品を含む農林水産物等(2条1項。酒類・医薬品・医薬部外品・化粧品・再生医療品等製品を除く)について、その生産地の地域の自然的・人文的・社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質・製法・社会的評価等の独自で多彩な特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護するための「地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度」が創設されました。この制度により、これまで、120産品が登録されています(令和4年10月現在)。
この地理的表示制度では、生産者団体が、地域ならではの要因との結び付きを有する産品について、生産地や特性とともに、農林水産大臣の登録を受けます(7条。産品に関する基準について2条2項・13条1項・同3項等、名称に関する基準について2条3項・13条1項4号等、生産者団体や生産方法に関する基準について2条4項・同5項・13条1項1号・同2号等)。その生産者団体の構成員及びその産品を販売等する者は、その地理的表示やGIマークという統一マークを使用することができ、不正使用については、行政が監視・取締りを行います。農林水産大臣は、不正使用者に対し、措置命令を発することができ(5条)、この命令に違反した場合には罰則があります(39条・40条・43条)。なお、地理的表示は、日本と同水準のGI制度を有する外国との相互保護の国際約束により、海外においても保護されます。
登録を受けた生産者団体は、構成員が行う生産の手順や体制が、基準に適合して行われるように検査等を実施しなければなりません(生産行程管理業務。2条6項)。生産行程管理業務に対しては、農林水産大臣による立入検査等(34条)や、措置命令(21条)・登録の取消し(22条)などが行われます。
このように、「地理的表示保護制度」は、産品の名称・ブランドを保護するものですが、それと共に、登録によってその産品の高い価値が再認識され、ビジネスの拡大や地域の活力向上につながっています。
(8)特定商取引法(特定商取引に関する法律)
特定商取引法は、特定の形態の取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引、訪問購入)について一定の規制を定め、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。特定商取引法では、取引形態ごとに、事業者が守らなければいけないことが規定されています。
通信販売の表示に関わる規制としては、広告における一定事項の表示義務(11条)や、虚偽・誇大広告の禁止(12条)などが定められています。
令和3年の改正では、申込み段階においても、申込みのために事業者が定める様式の書面やインターネット通販で表示する映像面(最終確認画面)(このような書面や映像面を「特定申込みに係る書面等」といいます)において申込者が一定の情報を確認できるように義務付けるとともに(12条の6第1項)、特定申込みに係る書面等において人を誤認させるような表示の掲載を禁止する規定が新設されました(12条の6第2項)。この規定に違反した場合には、申込者は申込みの意思表示を取り消すことができます(15条4)。
また、通信販売の申込みに関しては、「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」が禁止されています(14条1項2号)。その具体的内容として、インターネット通販の申込みの際に、顧客が、申込みの内容を容易に確認し及び訂正することができるようにしていないことと規定されています(施行規則16条1項)。この規定の解釈について、消費者庁がまとめた「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220622_08.pdf)によると、例えば、最終確認画面において、注文内容を容易に確認できない場合や、訂正するための手段(「変更」、「注文内容を修正する」、「前のページへ戻る」などのボタンの設定)が提供されていない場合が該当します。また、申込者が自分で変更しない限り定期購入契約として申し込むように予め設定してあり、注意していないと申込内容を認識しないままに申し込んでしまうようになっている場合も、該当するおそれがあるとされています。
特定商取引法における通信販売に関する規制に違反すると、業務改善の指示(14条)、業務停止命令(15条1項)、業務禁止命令(15条の2)などの対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります(70条、72条、74条等)。
誇大広告等をする行為や、特定申込みに係る書面等において表示をせず又は不実の表示をする行為、同書面等において人を誤認させるような表示をする行為などを不特定多数の者に行い又は行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し、行為の差止請求をすることができます(58条の19)。
(9)その他 条例等
自治体が、条令によって食品の表示について規制を行っている場合があるので注意が必要です。例えば、東京都では、東京都消費生活条例に基づき、法令で規定のない品目又は事項について表示の基準を策定し、基準にあった表示をするよう事業者に義務付けています。
おわりに
以上、食品の表示・広告に関する法規制について概観してきました。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- えん下困難者用食品について
- 特別用途食品について
- 経口補水液について
- 遺伝子組換え食品の表示制度について
- 食品添加物をめぐる規制
- 食品衛生法の改正について
- 食品表示基準の弾力的運用 — 令和6年能登半島地震を受けて
- 食品表示法に基づく食品表示制度
- 広域的な食中毒事案への対策強化について~改正食品衛生法①~
- HACCPに沿った衛生管理の制度化~改正食品衛生法②~
- 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度等について~改正食品衛生法③~
- 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について~改正食品衛生法④~
- 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設について~改正食品衛生法⑤~
- 食品等の自主回収報告制度について~改正食品衛生法⑥~
- 輸入食品の安全証明の充実~改正食品衛生法⑦~
- 原料原産地表示制度の改正について
- 景品表示法における「表示」について
- 食品に関して景品表示法違反が問題となった実例